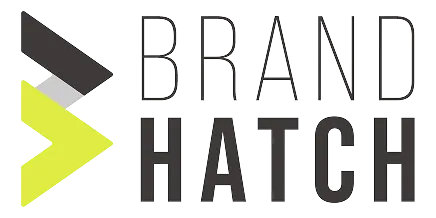現代のビジネスにおいて、SNSは単なる流行ではなく、企業成長を支える重要な戦略ツールです。
しかし、多くの中小企業では、知識や人手の不足から本格的な運用に踏み出せずにいるでしょう。
本記事では、SNS運用のメリット・デメリットから、成果を見える化するKPI設定、自社に合ったプラットフォームの選び方をご紹介します。
さらに、BtoB・BtoCそれぞれに最適な戦略もまとめました。
SNS運用で、集客や認知拡大などを成功させたい担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
1. なぜ今、企業のSNS運用が重要なのか?

SNSはもはや個人の娯楽ではなく、企業にとって顧客との重要な接点となっています。
特に、若年層の消費行動の変化や、従来の広告手法の限界を背景に、SNSを活用した情報発信の必要性が急速に高まっています。
ここでは、企業におけるSNS運用の必要性を、大きく2つに分けてまとめました。
1-1. 顧客は「広告」よりも「口コミ」を信頼する
かつては、テレビCMや雑誌広告が購買行動の大きなきっかけとなっていましたが、今やその主役はSNSへと移りつつあります。
総務省の「令和5年通信利用動向調査の結果」によると、インターネットの利用率は2022年で84.9%との結果が出ています。
企業がどれほど魅力的な広告を打ち出しても、実際のユーザーによるレビューや投稿、いわゆるUGC(ユーザー生成コンテンツ)の影響力には敵いません。
顧客は「企業が発信する情報」よりも「他者のリアルな体験談」に強く反応し、それを購入判断の基準にしています。
SNS上での評判が、ブランド価値や売上を左右する時代において、口コミの場としてのSNSを軽視することは、企業の成長機会を逃すことに直結するといえるでしょう。
1-2. 従来の広告手法だけではリーチできない層へのアプローチ
現在のメディア環境では、テレビや新聞といったマスメディアに対する接触時間が減少し、SNSに多くの時間を費やす傾向が見られます。
このようなメディア消費の変化は、従来の広告では届かなかった層、特に若年層にリーチするためには、SNSの活用が不可欠であるといえるでしょう。
SNSは、企業が顧客の日常の中に自然に入り込める数少ないチャネルの1つです。
だからこそ、今このタイミングでのSNS運用は、未来の顧客とつながるための戦略的な一手として、あらゆる企業に求められています。
2. SNS運用で得られる7つの戦略的メリット

SNS運用には、単なる情報発信にとどまらない多くのメリットがあります。
ここでは、企業活動における具体的な7つの戦略的価値を整理し、それぞれのメカニズムと実践的な効果を解説します。
2-1. 低コストで潜在顧客への認知を拡大できる
SNSは、広告やチラシといった従来の手法に比べて、圧倒的に低コストで運用を開始できます。
投稿が共感や興味を呼べば、ユーザーの「シェア」や「リツイート」によって情報が一気に拡散し、まだ接点のなかった潜在顧客層にまで届く可能性が広がります。
特に、企業の理念や独自のストーリーを盛り込んだ投稿が「バイラルヒット」することで、広告費をかけずに大規模な認知を獲得することも夢ではありません。
費用対効果に優れたマーケティングチャネルとして、SNSの活用価値はきわめて高いといえるでしょう。
2-2. 企業の価値観や世界観を伝え、ブランディングを強化する
SNSは、企業が自らの「らしさ」を伝えるのに最適なメディアです。
製品開発の裏話、社員の日常、企業のビジョンなど、公式サイトや広告では伝えきれない人間味あるストーリーを発信できるでしょう。
こうした情報発信は、単なる商品・サービスの紹介にとどまらず、企業の世界観や価値観に共感するファンの獲得に繋がります。
ブランドの人格を感じさせるような投稿が、競合との差別化において大きな武器となるのです。
2-3. 双方向の対話で顧客エンゲージメントを高め、ファンを育てる
SNSは一方通行の情報発信ではなく、ユーザーとの「会話」が可能な場です。
投稿へのコメントに返信したり、ダイレクトメッセージに対応したりすることで、企業と顧客の間に信頼関係が生まれます。
特に、迅速で丁寧な対応がされているアカウントは「感じのよい企業」としてユーザーに記憶され、リピーターや紹介へとつながる可能性が高まるでしょう。
日々のやり取りの中から、長期的なファンを育てられるのが、SNSならではの魅力です。
2-4. ECサイトやオウンドメディアへの新たな流入経路を確保する
SNSアカウントのプロフィール欄や投稿内に、ECサイトや自社のブログ、キャンペーンページへのリンクを設置することで、新たな集客導線を築けます。
特に、商品の魅力を伝える投稿と購入リンクを組み合わせることで、ユーザーの興味を引いてから購入アクションまでをスムーズに誘導できるでしょう。
SNSは「発信の場」であると同時に、ECサイトなどへつなげる「橋渡し役」としても活用可能です。
2-5. 顧客のリアルな声を収集し、商品開発や改善に活かす
SNS上では、自社の商品やサービスを実際に使ったユーザーの声が、投稿として蓄積されます。
こうしたUGCは、企業にとって非常に貴重なフィードバックの宝庫です。
例えば「○○が便利だった」「△△が使いにくい」といった生の声を収集・分析することで、商品開発や改善に直接反映させられるでしょう。
また、UGCを活用したプロモーション展開も、信頼性の高いマーケティング手法として注目されています。
2-6. 企業の文化や働く人の魅力を発信し、採用力を強化する
求人票だけでは伝えきれない、企業のリアルな雰囲気や働く人の魅力をSNSで発信することで、求職者に対して強力な訴求が可能となります。
例えば、オフィスの様子や社内イベントの紹介、社員インタビューなどを通じて「どんな人が働いているのか」「どんなカルチャーがあるのか」を具体的に伝えられるでしょう。
これにより、企業に共感を持った応募者の増加や、入社後のギャップを減らすなどの効果が期待できます。
SNSは、採用ブランディングの面でも強力な武器になるでしょう。
2-7. 広告に頼らない情報発信で、長期的なコスト削減に繋がる
SNSでフォロワーを増やし、定期的に情報発信を行うことで、「届けたい情報を、届けたい人に、無料で」届けられるようになります。
これは、広告に依存せずにマーケティングを展開できる体制を意味します。
一度フォロワーとの関係性を築ければ、その後は新商品情報やイベント案内などを、広告費をかけずに発信できるのです。
このようにSNSは、中長期的に見たマーケティングコストの削減に、大きく貢献する手段といえるでしょう。
3. SNS運用を始める前に知るべき3つのデメリット

SNSは効果的なマーケティング手段ですが、運用するにはいくつかの注意点や課題もともないます。
ここでは、企業がSNSを運用する前に必ず押さえておきたい3つのリスクと、それぞれに対する備えについて解説します。
3-1. 炎上による企業イメージの毀損リスクと対策
SNS最大のリスクの1つが「炎上」です。
不適切な表現や軽率な投稿、あるいはユーザーからのコメント対応の不備によって、一気に批判が拡大し、企業の信頼を損なう可能性があります。
特に昨今は、過去の投稿まで掘り返されて問題視されるケースも珍しくありません。
これを防ぐためには、担当者の感覚に頼らず、社内で明確なSNS運用ガイドラインを整備することが不可欠です。
投稿前のダブルチェック体制や、トラブル時の対応フローも事前に設けておくと安心です。
3-2. 継続的な運用には人的・時間的コストがかかる
SNS運用は「無料で始められる」点が魅力ではありますが、実際にはコンテンツ企画・投稿作成・ユーザー対応・分析と、多岐にわたる作業が発生します。
これらを継続的に行うには、ある程度の人手と時間が必要であり、片手間では成果を上げにくいのが現実です。
特に中小企業では、他業務と兼務している担当者が限られたリソースの中で運用することが多く、モチベーションやクオリティの維持が課題になることもあります。
あらかじめ必要な工数を見積もり、可能であれば部分的に外部の力を借りる選択肢も検討しましょう。
3-3. 成果が出るまでには中長期的な視点が必要
SNS運用は、即効性のある施策ではありません。
アカウントを開設してすぐに売上が上がるということはなく、フォロワーとの信頼関係を築き、ブランドへの理解や好感を積み重ねていく過程が不可欠です。
特に企業アカウントは、個人に比べてフォローされにくい傾向があるため、初期の成果が見えにくく、途中で運用を断念してしまうケースもあります。
しかし、SNSは長く続けることでこそ資産となり、徐々に着実な効果を発揮していきます。
最低でも、半年〜1年単位での運用を前提に取り組む姿勢が求められるでしょう。
4. SNS運用の担当者に求められる5つのスキル

SNS運用は、戦略やツール以前に「誰が担当するか」で成果の大半が左右されるといっても過言ではありません。
成果を出すためにSNS担当者に必要な主要スキルは、下記の5つです。
- 企画力と情報感度
SNSは常にトレンドが移り変わる世界です。企業として発信すべき情報と世の中の関心を掛け合わせ、共感を呼ぶ投稿テーマを見極める力が求められます。
- 文章力と表現センス
限られた文字数の中で、伝えたい情報を簡潔かつ魅力的に表現するには、日頃からの言葉選びの訓練が必要です。特にBtoCでは、ユーザーの目を惹くコピーやテンポのよい言い回しが効果を左右するでしょう。
- デザイン・画像編集スキル
テキストだけでなく、視覚的な印象が投稿の反応率を大きく左右するため、Canvaなどのツールを使って、簡単な画像を自作できると運用の自由度が高まります。
- コミュニケーション能力
コメントやDMへの対応、炎上リスクの想定、ユーザーとの関係構築など、受け手を意識した丁寧なやりとりがブランドへの信頼につながります。
- 分析・改善力
インプレッション数やエンゲージメント率などの指標を元に、「なぜ伸びたのか、なぜ反応が鈍かったのか」を読み解き、次の改善アクションへとつなげていく視点が求められます。なお、PDCAとは「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」の4段階を繰り返し、業務の質を継続的に高めていく手法です。
これらのスキルを一人で完璧に持つ必要はありません。
大切なのは、自社のリソースや課題に応じて、チームで分担する、あるいは外部と連携する柔軟な体制を築くことで、SNSの力を最大限に引き出せるでしょう。
5. SNS運用のメリットを最大化する「効果測定」とKPI設定

SNS運用を成功させるうえで欠かせないのが、「やりっぱなし」を防ぐための効果測定と、目的に応じたKPI(重要業績評価指標)の設定です。
この章では、運用成果を正しく把握し、改善につなげるための基本的な考え方と実践方法を解説します。
5-1. なぜ効果測定が不可欠なのか?「やりっぱなし」を防ぐKPIの重要性
SNSは、投稿して終わりでは成果が出ません。
むしろ、投稿後のデータ分析と改善のサイクルこそが、運用の成否を分けるポイントです。
例えば、どの投稿が多くの人に届いたのか、どの内容がユーザーの反応を引き出したのかといったデータは、次の投稿戦略のヒントになります。
ここで重要になるのがKPIです。
KPIは「目指すべき成果を数値で表す指標」であり、感覚ではなく客観的な判断基準として、目標達成に向けた羅針盤となります。
目的が曖昧なままでは、どのデータを見ればよいのかも不明確になりがちです。
まずは目的を明確にし、それに紐づいたKPIを設計することが、効果的なSNS運用の出発点となるでしょう。
5-2. 【目的別】SNS運用のKPI設定例
SNSの運用目的は企業によって異なりますが、大きく分けると「認知拡大」「エンゲージメント向上」「売上貢献」の3つに分類されます。
それぞれの目的に対して、追うべきKPIも異なります。
以下は代表的な例です。
| 目的 | 主要KPI | KPIの具体例 |
| 認知拡大 | ・インプレッション数 ・リーチ数 ・フォロワー数 | ・インプレッション数=投稿の表示回数 ・リーチ数=投稿を見たユニークユーザー数 ・フォロワー数=ブランドのファン数 |
| エンゲージメント向上 | ・エンゲージメント率 ・UGC数 ・コメント数 | ・エンゲージメント率=(いいね+コメント+シェア)÷インプレッション数 ・UGC数=ユーザーの関連投稿数 ・コメント数=対話の活発度 |
| 売上貢献 | ・ウェブサイトクリック数 ・コンバージョン数 | ・ウェブサイトクリック数=SNS経由の遷移数 ・コンバージョン数=購入・問い合わせ・資料請求などの成果件数 |
このように、目的ごとにKPIを明確にすることで、「今何を強化すべきか」「どこに改善余地があるか」が可視化され、より戦略的な運用が可能となるでしょう。
6. SNS運用におけるプラットフォームの特徴と比較

SNS運用を始めるうえで「どのプラットフォームを選ぶか」は非常に重要な意思決定です。
ここでは、選定の際に押さえておきたい視点と、主要5大SNSの特徴をBtoB・BtoCそれぞれの観点から比較しました。
6-1. プラットフォーム選定で失敗しないための3つの視点
SNS選定で迷ったときは、以下の3つの視点を軸に考えることで、自社に最も合ったプラットフォームを絞り込めます。
- ターゲットユーザーはどこにいるか?
自社の顧客層(年齢、性別、興味関心など)が日常的に利用しているSNSを選ぶことで、情報が届く確率が大きく高まります。 - 自社の商材やコンテンツとの相性は?
写真・動画などのビジュアル中心の商材ならInstagram、速報性や話題性を活かしたいならX(旧Twitter)など、コンテンツの性質とSNSの特徴が合っているかを確認しましょう。 - 運用目的は何か?
認知拡大・採用強化・販売促進など、目的に応じて向いているプラットフォームは異なります。
目的に合致するSNSを選定することで、成果が出やすくなります。
6-2. 主要5大SNSの特徴を徹底比較【BtoB/BtoC別おすすめ度付き】
以下は、国内で主要な5つのSNSについて、ユーザー層や得意分野、ビジネス活用の特徴を整理した比較表です。
BtoBとBtoC、それぞれの活用における「おすすめ度」も併記しています。
| SNS | 主要ユーザー層 | BtoBおすすめ度 | BtoCおすすめ度 | 得意なこと・メリット |
| LINE | 全世代(特に30代~50代) | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ・顧客サポート、リピーター施策、1対1の情報配信が得意 ・幅広い世代にリーチ可能 |
| X(旧Twitter) | 10代~40代(男女問わず) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ・拡散力とリアルタイム性が高く、話題作りやキャンペーン向き ・企業の「人となり」も伝えやすい |
| 20代~30代女性が中心 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ・写真・動画でのブランディングに強く、ビジュアル商材(アパレル・コスメ・飲食など)と好相性 | |
| 30代以上のビジネスパーソン | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ・実名登録による信頼性が高く、BtoBでの情報発信やコミュニティ形成に適している | |
| TikTok | 10代~20代(若年層) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ・ショート動画によるトレンド発信が得意 ・若年層向け商材の認知獲得に非常に効果的 |
たとえば、BtoB企業で採用や商談獲得を目指す場合は、FacebookやXの活用が有効です。
一方、BtoCで若年層の消費者をターゲットにするなら、InstagramやTikTokが大きな力を発揮するでしょう。
LINEは、幅広い年代へのリマインドや再来の促進に優れており、既存顧客との関係維持にも効果的です。
なお、すべてのSNSを一度に始める必要はありません。
リソースに応じて、最も成果に直結しそうな1〜2つに集中することが、運用の成功につながります。
目的と相性を冷静に見極め、自社にとって「価値のある場」を選びましょう。
7. 失敗事例から学ぶ!SNS運用を成功させるための4つのポイント

SNS運用で成果を出すには、成功パターンだけでなく失敗事例から学ぶことがとても重要です。
この章では、企業が陥りがちな典型的な失敗パターンと、それを回避し成果を上げるための具体的な成功法則をご紹介します。
7-1. あなたは大丈夫?SNS運用でやりがちな3つの失敗パターン
まずは、SNS運用でやりがちな3つの失敗パターンを見てみましょう。
7-1-1. 目的が曖昧なまま始めてしまう
「とりあえず始めてみよう」とSNSアカウントを開設し、投稿を続けているものの、何を目指しているのかが不明確で、社内からも評価されず、モチベーションが低下してしまうケースです。
最終的には更新が止まり、「幽霊アカウント」になってしまうことも珍しくありません。
7-1-2. 一方的な宣伝・広告ばかりを投稿する
商品の紹介やキャンペーン情報だけを機械的に投稿していると、ユーザーとの距離感は縮まりません。
SNSはコミュニケーションの場であり、「売り込み」ではなく「共感」が求められるという本質を見失うと、フォロワーの反応は冷ややかになります。
7-1-3. データを見ずに感覚だけで運用する
「なんとなくよさそう」「バズったっぽい」といった感覚に頼った運用では、改善の方向性が見えず、行き当たりばったりになりがちです。
効果測定を怠ることで、労力をかけても成果に結びつかない状況に陥るため注意しましょう。
7-2. 失敗を避けて成果を出すための4つの成功法則
前章の失敗を踏まえ、SNS運用で成果を出すために意識すべき4つの成功法則をご紹介します。
どれも基本的なことですが、実践することで着実に成果につながるでしょう。
7-2-1. 目的とKPIの明確化
SNSを運用する目的(認知拡大、ファン育成、採用強化など)を明確にし、その目的に合ったKPIを設定することで、運用の方向性と評価基準が定まります。
「何のためにやっているのか」がブレなければ、チームの連携も強化されるでしょう。
7-2-2. ペルソナ(ターゲット顧客像)の設定
漠然とした「一般ユーザー」ではなく、具体的なペルソナを設定することで、投稿の内容やトーンが明確になります。
例えば「30代の子育て中の女性」や「BtoBで働くマーケティング担当者」など、狙うべき相手に刺さる情報を届けやすくなります。
7-2-3. 価値あるコンテンツの継続的提供
フォロワーが「役に立つ」「面白い」と感じる情報を定期的に発信することが、信頼や関心を生み出します。
商品紹介だけでなく、ノウハウ・裏話・社員紹介など、企業の価値や姿勢が伝わる内容を織り交ぜましょう。
7-2-4. データに基づくPDCAサイクルの実行
投稿ごとの反応やKPIの変化を定期的に振り返り、改善を積み重ねていくことが成果のカギです。
計画→実行→評価→改善というPDCAを小さく回すことで、運用の質が着実に高まります。
これらのポイントを意識することで、SNS運用は単なる広報活動から、ビジネスに貢献する戦略的な取り組みへと進化します。
失敗を恐れず、学びを糧にしながら、一歩ずつ進めていきましょう。
8. まとめ
SNS運用は、正しく取り組めば企業にとってきわめて大きな価値をもたらす戦略的な武器です。
低コストで認知を拡大し、ブランドの世界観を伝えつつ顧客との関係を深めることで、採用や売上アップにつながります。
一方で、リソースの確保や効果測定といった課題もあり、それらを踏まえた計画的な運用が求められます。
最初から完璧を目指す必要はありません。
大切なのは、小さく始めて、データを見ながら改善を重ねていく姿勢です。
ぜひ、本記事を出発点として、SNS運用という新たな一歩を踏み出してみてください。
とはいえ、日々の業務に追われながら、データ分析から改善までを一貫して行うのは大変な労力がかかります。
「Brand Hatch株式会社」では、この戦略的なPDCAサイクル運用をすべて代行し、お客様のアカウントを継続的に成長させます。
感覚的な運用から脱却したい方は、ぜひご相談ください。