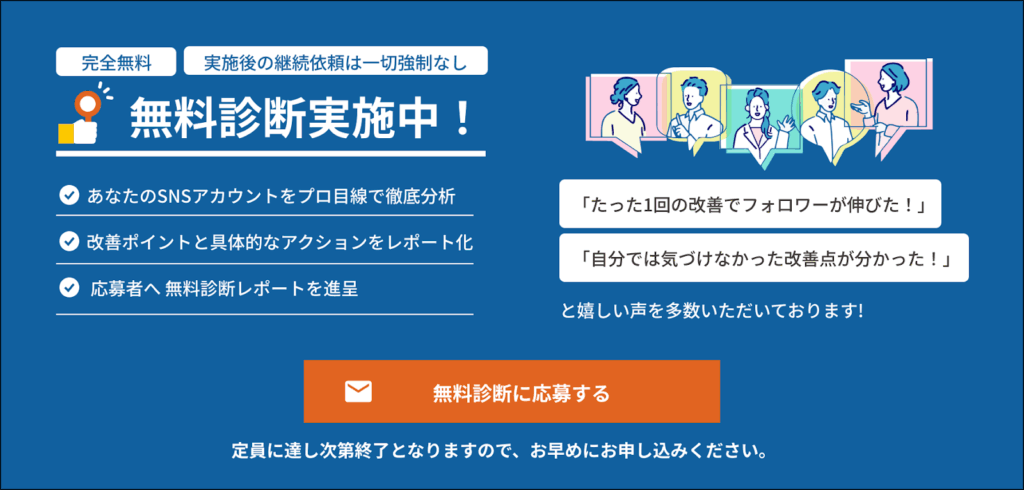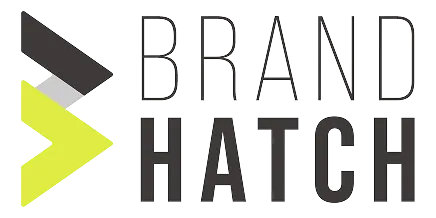「塾の集客にSNSは効果的なのか?」
「SNSをどう活用すればよいのか?」
上記のようにお悩みではありませんか?
少子化により生徒数が減る一方で、競合の塾は増え続けており、効率的な集客が欠かせません。
今やSNSは子どもや保護者との信頼関係を築き、塾の魅力を伝える重要なツールとなっています。
この記事では、塾の集客にSNSが必要な理由や、InstagramやTikTokなど主要SNSの特徴、塾の集客における成功事例、効果的な運用方法、失敗しやすい点などを解説します。
成果につながる戦略的な運用のヒントを知りたい塾経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
1. なぜ今、塾の集客にSNSが必要なのか?

近年、塾の集客方法は大きく変化しており、中でもSNSでの集客に注力する塾が増えています。
ここでは、なぜ今、塾の集客にSNSが必要とされているのかを解説します。
1-1. 子どもや保護者のSNS利用時間が年々増加しているから
近年、子どもや保護者がインターネットで情報収集をする際、SNSが大きな役割を果たすようになってきました。
総務省の「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(概要)」によれば、10代・20代を中心にSNSの利用時間は非常に大きな割合を占めており、SNSから情報を得る機会が多くなっています。
特に中高生にとってSNSは日常的なコミュニケーションツールであり、友人同士のやり取りや最新情報を収集する場として欠かせない存在です。
また、30代や40代の保護者世代においても、テレビや新聞よりインターネット利用時間の方が多くなっており、中でもSNS利用割合が多くを占めています。
その結果、塾選びに関する口コミや体験談もSNSを通じて目にする機会が自然と増えているのです。
このように、ターゲット層が日常的に利用している場所に塾の情報を発信すれば、接点を自然に生み出せます。
SNS活用は、現代の集客において欠かせない取り組みとなっているのです。
参考:令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(概要)(総務省情報通信政策研究所)
1-2. コストを抑えて集客できるから
塾の集客にSNSを活用する大きな利点は、従来のチラシや看板広告に比べて集客コストを抑えられる点です。
アカウント開設は無料で、少額からでも広告配信が可能です。
例えば、地域や年齢を指定して配信すれば、ターゲット層に直接アプローチできます。
さらに、表示回数やクリック数をすぐに確認できるため、成果を把握しながら改善を重ねられる点も特徴です。
継続的に運用することでデータが蓄積され、より効果的な配信が可能になり、費用対効果も向上します。
1-3. 「ファン化」しやすいから
SNSは単なる情報発信の場だけではなく、塾と子ども・保護者の距離を縮めるコミュニケーションの場でもあります。
塾の雰囲気や講師の人柄を自然に伝えられ、投稿に対するコメントや「いいね」を通じて双方向の交流が生まれるでしょう。
また、日常の取り組みやイベントを継続的に発信することで、信頼と親近感が高まり、塾への好意的な感情、いわゆる「ファン化」にもつながります。
ファンになった子どもや保護者は、新規入会や紹介にも結びつきやすく、安定した集客基盤を築けるのです。
1-4. 認知拡大につなげられるから
SNSは拡散性が高く、塾の存在をまだ知らない層にもアプローチできるのが特徴です。
投稿のシェアや「いいね」を通じて思わぬ形でバズり、認知度を一気に高められる場合もあります。
さらに、地域名などを入れたハッシュタグを活用すれば、関心のある子どもや保護者に効率的にリーチできます。
従来の広告では届きにくかった潜在層にもアプローチできるため、SNSは集客だけでなく塾のブランド認知向上にも有効な手段となるのです。
2. 塾集客に活用できる6つのSNS

塾の集客に効果的なSNSは、目的やターゲット層によって適した媒体は異なります。
ここでは代表的な6つのSNSについて、その特徴と活用方法をご紹介します。
2-1. Instagram
Instagramは写真や動画で塾の雰囲気を直感的に伝えられるため、信頼獲得に効果的です。
教室の様子や講師の人柄、合格実績、イベントの裏側などを発信することで、「通いたくなる理由」を視覚的に示せます。
ストーリーズやリールで学習ノウハウやショート解説を投稿すれば、保存や共有によって接触頻度が増え、ファン化につなげることも可能です。
さらに、ハッシュタグや位置情報を活用すれば近隣ユーザーにも届きやすく、子どもと保護者の双方に認知を広げられます。
広告機能を使えば、地域や年齢を絞った訴求も可能です。
プロフィールに体験予約や問い合わせの導線を設け、DMでの相談に丁寧に対応すれば、集客効果をさらに強化できます。
参考:Instagram
2-2. Facebook
Facebookは30代で39.2%・40代で38.6%・50代で32.1%と、ほかの世代に比べて利用者が多く、保護者層に情報を届けやすい媒体です。
塾の理念や教育方針、卒業生の声、イベント報告などを発信することで信頼感を高められます。
写真や動画を添えると内容が伝わりやすく、シェアによって地域内での認知拡大にもつながります。
また、授業風景や日常の取り組みといった塾ならではの発信も、保護者に安心感を与える有効なコンテンツです。
グループ機能を使えば、保護者同士のコミュニティ形成も促せます。
さらに、広告配信では年齢や地域、興味関心を細かく指定できるため、自塾に合う層に効率的にリーチが可能です。
信頼性の高い情報の発信と精度の高い広告運用で、入会検討段階の保護者に強力にアプローチできる点もpFacebookの強みです。
参考:Facebook
参考:令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(概要)(総務省情報通信政策研究所)
2-3. TikTok
TikTokは短尺動画を中心としたSNSで、中高生をはじめとする若年層へのリーチに優れたSNSです。
授業の工夫や勉強のコツをテンポよく紹介すれば、楽しみながら学べる印象を与えられ、興味を持ってもらいやすくなります。
エンタメ要素を交えた動画は拡散されやすく、トレンド音源やハッシュタグを活用することで、塾の知名度を広げられる可能性があります。
また、講師や生徒が登場する動画は親近感を生み、塾の雰囲気をリアルに伝えられる点も強みです。
関心の高いユーザーに動画が届きやすいため、潜在層への認知拡大から集客のきっかけづくりまで幅広く対応できるのが特徴です。
参考:TikTok
2-4. X
Xは拡散性の高さが最大の特徴で、短文や画像を組み合わせた投稿が瞬時に多くのユーザーへ届きます。
塾の最新情報やキャンペーンなどをタイムリーに発信することで、入塾に関心を持つ子どもや保護者に直接アプローチが可能です。
リポストや引用によってコミュニティ内で話題化しやすく、自然な口コミ効果も期待できます。
また、「#高校受験」「#受験生」などハッシュタグを工夫することで検索流入の増加も狙えるでしょう。
さらに、話題になっているトピックやハッシュタグに合わせて投稿することで、通常は接点のないユーザーのタイムラインにも表示されやすくなり、認知拡大につながります。
Xは、リアルタイムな発信と拡散を同時に実現できる有効な媒体です。
参考:X
2-5. LINE
LINE公式アカウントは幅広い世代に利用されているため、塾の集客において欠かせないツールです。
友だち登録をしてもらえば、最新情報やイベント案内を直接届けられるだけでなく、保護者とのダイレクトな連絡手段としても活用できます。
メッセージ配信は開封率が高く、チラシやメールに比べて確実に情報を届けられるのが特徴です。
また、体験授業やイベントの申し込みフォームと連携させることで、ストレスなく申し込み手続きも完了できます。
さらに、クーポン配布や学習に役立つ情報を定期的に発信することで、保護者との関係を深められ、リピーター獲得にも効果的です。
チャット機能を使えば問い合わせ対応も迅速に行え、信頼感の向上につながります。
継続的な情報発信と双方向のやり取りを通じて、見込み顧客を入塾へと導けるのがLINE公式アカウントの魅力です。
参考:LINE
2-6. YouTube
YouTubeは動画を通じて塾の魅力を深く伝えられ、集客において高い効果を発揮する媒体です。
授業の一部を公開したり、講師による学習アドバイスや勉強法を紹介したりすれば、専門性や指導力を具体的に示せます。
実際の授業風景やイベントの様子を映像で届けることで、子どもや保護者は塾の雰囲気や講師の人柄をリアルに感じられ、安心感や信頼感につながります。
さらに、YouTubeは検索結果の上位に表示させるSEO対策も行いやすく、塾を知らない層への認知拡大も可能です。
公開した動画は資産として長期的に残るため、継続的に視聴され、入塾のきっかけになることもあります。
チャンネル登録者を増やすことで定期的な接点を作り出し、長期的な集客基盤を作れるのがYouTubeの強みです。
参考:YouTube
3. SNSを活用した塾の集客成功事例5選

実際にSNSを活用して成果を上げている塾は数多くあります。
SNSを活用して集客に成功した事例を5つご紹介しますので、効果的な取り組み方をイメージしてみてください。
3-1. 河合塾
河合塾は、難関大学合格を目指す学生をサポートする三大予備校の一つです。
大手予備校としての強みを活かし、複数のSNSを戦略的に運用している点が特徴です。
Instagramでは学習アドバイスや授業風景の動画を発信し、受験生に役立つ情報とともに教室の雰囲気を伝えています。
Xでは模試やイベント情報をタイムリーに紹介し、自社ブログへ誘導する導線を設けています。
媒体ごとに役割を分けることで、幅広い層と効率的に接点を増やし、信頼感と集客効果の向上につなげている点は、参考になるポイントです。
3-2. 明光義塾 板倉東洋大前教室
群馬県邑楽郡板倉町にある、明光義塾の板倉東洋大前教室では、「明光いたくら」のアカウント名でTikTokを運用しています。
短尺動画ならではのテンポ感を活かして授業風景やイベントを紹介することで、塾の風通しのよさや親しみやすさを伝え、安心感を与えている点が特徴です。
さらに、サボりを誘惑してくる「サボロー」というキャラクターなどのエンタメ要素を取り入れた動画は拡散性が高く、認知度向上にも貢献しています。
TikTokの特徴を最大限に活かし、集客につなげている好例です。
3-3. 武田塾
武田塾は「授業をしない塾」という独自の学習法を打ち出している学習塾です。
YouTubeでは勉強法や受験に役立つ情報を出し惜しみせず公開し、さらに1日2回の動画投稿を継続することで、受験生の高い信頼を獲得しました。
また、Instagramでは同じテーマのコンテンツを扱い、デザインやトーンも統一し、一貫したブランドイメージを形成しています。
複数のSNSを戦略的に組み合わせ、情報提供とブランディングを同時に行いながら全国的な知名度向上と集客に成功しています。
3-4. 長崎医大アカデミー
長崎医大アカデミーは、講師全員が現役医学部生という強みを持つ個別指導塾です。
開業当初からLINE公式アカウントを導入し、学習のヒントやイベント情報を頻繁に配信することで、生徒や保護者との接点を継続的に築いてきました。
その結果、開業わずか6カ月で目標生徒数を達成するなど、短期間で大きな成果を上げています。
専門性の高い講師陣と、LINEを軸にした継続的な情報発信を組み合わせた成功事例です。
3-5. 学習塾 伸学会
伸学会は自由が丘や目黒など東京の5箇所で教室を運営する、中学受験専門の学習塾です。
Facebookを起点にYouTubeの保護者向け動画へ誘導する仕組みを構築し、塾の教育方針や授業の雰囲気をわかりやすく発信しています。
さらに、投稿から公式LINEへスムーズに遷移できる導線を設け、問い合わせや相談がしやすい環境を整備しました。
複数のSNSを連携させることで、情報発信とコミュニケーションを強化し、信頼感を高めながら入会検討者を効果的に獲得している好例です。
4. 塾におけるSNS集客のポイント

SNSで効果的に集客を行うには、媒体ごとの特性を理解し、戦略的に運用することが重要です。
ここでは塾の集客にSNSを活用する際に意識すべき具体的なポイントを解説します。
4-1. 目的を明確にして運用を一貫させる
SNSを塾の集客に活用する際は、まず「体験授業の申し込みを増やす」「資料請求を増やす」など、具体的なゴールを明確にすることが欠かせません。
地域での認知度向上や、子どもと保護者の関係強化など、目的によって発信内容や媒体の選び方は大きく変わります。
目的が曖昧なままでは投稿が場当たり的になり、トーンやテーマもぶれやすく、成果を実感しにくくなります。
明確な目的を定めれば、フォロワー数やエンゲージメント率、サイト流入数といったKPIを設定しやすくなり、効果測定と改善につなげることが可能です。
さらに、目的に沿った一貫性のある発信を続けることで、塾のブランドイメージを形成でき、信頼感の向上にもつながります。
また、SNS運用は単独で考えるのではなく、Webサイト運営やWeb広告運用といった他施策と連動させることで、集客効果も最大化できます。
目的を明確にしたうえで全体戦略に組み込むことが、SNS運用を成果に結びつけるポイントです。
4-2. 塾ならではの投稿ネタを用意する
SNSで塾の魅力を効果的に伝えるには、一般的な情報発信にとどまらず「塾ならではの投稿ネタ」を意識することが重要です。
授業風景や講師の紹介といった投稿は、人柄や教育姿勢を伝えられるため、子どもや保護者に安心感を与えます。
さらに、合格体験談や模試結果のシェアは信頼性を高める強力なコンテンツであり、受験を控える層の関心を集めやすいテーマです。
また、勉強法や受験アドバイスといったTips(コツ・ヒント)を発信すれば、フォロワーにとって役立つ情報源となり、塾の専門性も示せます。
イベントや講習の様子を写真や動画で紹介すれば、塾の活気や生徒同士の雰囲気をリアルに伝えることもできます。
さらに、教室掲示物や日常の取り組みを切り取ることで、誠実さや信頼感を積み重ねることも可能です。
こうした「現場感のある情報」を発信することで、大手予備校との差別化を図り、塾に通うイメージを具体的に描いてもらいやすくなります。
単なる宣伝ではなく、フォロワーの共感や信頼を育む投稿を継続することが、入塾につながる関係構築に重要なのです。
4-3. 写真・動画やハッシュタグで発信力を高める
SNSで塾の魅力を伝えるには、写真や動画の活用が効果的です。
教室の広さや清潔感、講師の表情、自習室の活気など、文字だけでは伝わりにくい要素を視覚的に示せるため、安心感や信頼につながります。
授業やイベントの様子をハイライトやビフォーアフター形式で紹介すれば、保存や共有が促され、継続的な接点を生み出すことも可能です。
4-4. 継続的に情報発信する
SNSを集客に活かすには、継続的な投稿が欠かせません。
ユーザーは日々膨大な情報に触れているため、定期的な露出がなければ存在を忘れられてしまいます。
ただし、どのSNSも同じ頻度で更新すればよいわけではなく、媒体の特性に応じた更新ペースを意識する必要があります。
例えば、Xはリアルタイム性が高いため毎日複数回の投稿が望ましい一方、InstagramやFacebookは週数回でも十分効果を発揮します。
YouTubeは制作に時間がかかるため、月数本の更新でも継続して発信することが大切です。
また、更新を継続するためにはスケジュール管理も重要です。
更新する曜日や時間帯を決めて仕組み化すれば、担当者の負担を減らしつつ、安定的に運用を継続できます。
定期的な発信は、塾のブランド力を高める要素となります。
5. SNSを活用した塾の集客で失敗しやすい原因
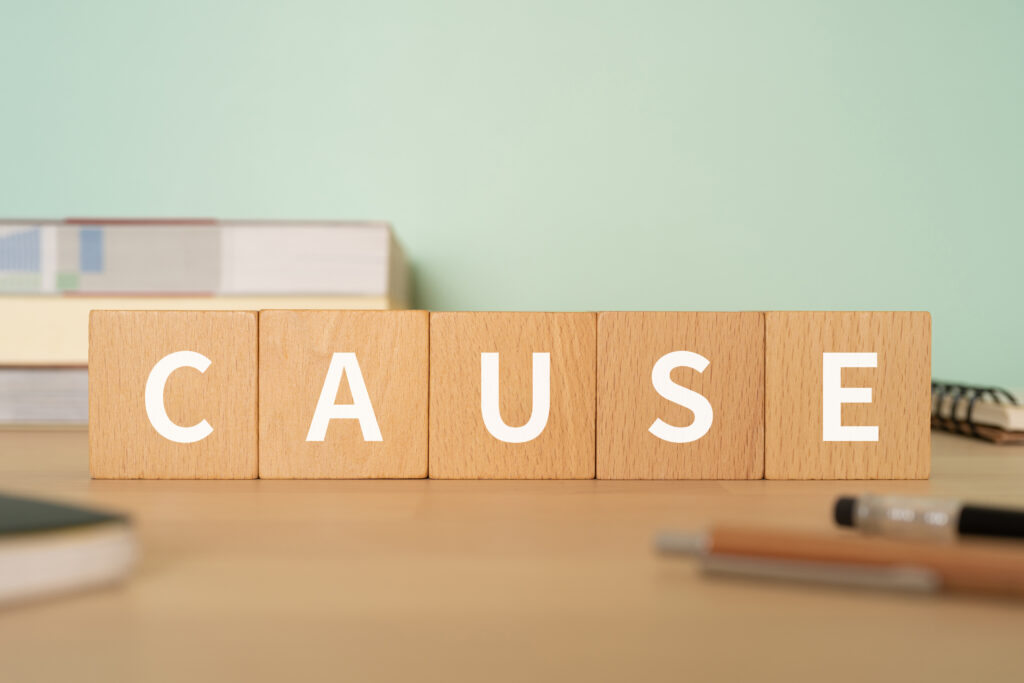
SNSは効果的な集客手段ですが、運用を誤ると逆効果になる恐れがあります。
ここでは塾が注意すべき失敗例をご紹介します。
5-1. 更新頻度が少ない
SNS運用でよくある失敗の一つが、投稿頻度が極端に少なくなってしまうことです。
長期間更新が止まると「この塾は活動していないのでは」と信頼性の低下につながります。
最低でも週1〜2回は更新を続け、最新情報や日常の様子を届けることが大切です。
継続的に発信することでフォロワーの関心を維持し、塾の存在を常に意識してもらえます。
5-2. 日記やお知らせばかりになってしまう
SNS投稿が日記や一方的なお知らせに偏ると、情報を受け取る側のメリットが限られます。
そのためユーザーには響かず、フォローや拡散も期待できません。
学習ノウハウや受験のコツ、合格体験談などを交えることで、塾の専門性や信頼性を示せます。
お知らせ投稿と役立つ情報をバランスよく組み合わせることで、フォロワーに継続的に関心を持ってもらえ、集客にもつながるでしょう。
5-3. 個人的すぎる内容を投稿してしまう
講師の私生活や趣味といった内容ばかりを投稿すると、塾の専門性が薄れ、ブランドイメージを損なう恐れがあります。
人柄を伝えること自体は有効ですが、あくまで学習や塾の魅力に関連した形で行うことが大切です。
そのためには、投稿方針をルール化し、発信基準を明確にしておく必要があります。
塾の価値や教育方針が伝わる投稿を中心に据えることで、信頼感を維持しながら効果的な運用につなげられます。
5-4. 個人情報に配慮していない
SNSで生徒の顔や名前を不用意に投稿すると、プライバシー侵害やトラブルにつながるリスクがあります。
発信前には必ず保護者の同意を得て、名前を伏せたり顔をスタンプやモザイクで加工したりといった配慮が欠かせません。
適切な対応を徹底することで、生徒や保護者との信頼関係を守り、長期的な集客にもつながります。
6. 塾集客のSNSは自社運用か?代行か?

SNS集客は、自社で運用するか専門会社に代行を依頼するかで成果や負担が大きく変わります。
ここでは両者の違いや特徴を整理し、塾に合った運用方法を検討するためのポイントをご紹介します。
6-1. SNS集客を自社で行うメリット・デメリット
SNS集客を自社で行うメリットとデメリットは、次のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・コストを削減できる ・授業風景や講師の人柄、生徒の様子などを伝えられる ・子どもや保護者とのダイレクトなコミュニケーションを取れる ・ノウハウが社内に蓄積される | ・投稿や編集、分析などのスキルが必要となる ・担当者の負担が大きくなる ・期待した成果が得づらい |
自社運用はコスト面や柔軟性で優れている一方、担当者のリソースやスキルに依存する点が課題です。
成功のためには、具体的な目標を定め、投稿スケジュールやルールを整備することが欠かせません。
6-2. SNS集客を代行に任せるメリット・デメリット
SNS集客を代行に任せるメリットとデメリットは、次のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・プロの品質で成果を安定化できる ・社内の負担を抑えつつ継続できる ・投稿の質にばらつきが出にくい ・中長期的な成果を積み上げられる ・投稿アイデアの幅が広がる | ・予算を確保する必要がある ・温度感や現場の雰囲気を反映させづらい ・コミュニケーションコストが増える |
社内に十分なリソースやノウハウがない場合や、成果を安定的に伸ばしたい場合には代行は有力な選択肢です。
目的や方針を明確に共有し、代行会社と連携して運用を進めることで、効率的かつ持続的に成果を高めることができます。
ただし、自社運用よりも費用がかかる傾向にあるほか、投稿案の確認や修正に時間が要する点などはデメリットです。
6-3. 塾の集客を依頼するSNS運用代行会社を選ぶ際のポイント
SNS運用代行会社を選ぶ際には、複数の観点から慎重に比較することが重要です。
まずは、戦略立案力を確認しましょう。
塾の目的やターゲットを踏まえて運用目的を設定し、成果につながる運用設計を具体的に提案できるかどうかが重要です。
特にSEOの知識や実績を持ち、検索流入とSNSを連動させた導線設計ができる会社であれば、効果を最大化しやすくなります。
次に重視したいのは、コンテンツの品質です。
文章やデザイン、動画編集まで一貫して対応できる体制があり、塾の魅力を的確に表現できるノウハウを持っているかどうかがポイントです。
教育業界での実績がある会社であれば、保護者や生徒に響く表現に強く、安心して任せられます。
さらに、効果測定と継続的な改善も欠かせません。
インプレッション数やクリック率、フォロワー数などの数値を定期的にレポートし、その結果をもとに改善策を提案できる会社であれば、運用の質を継続的に高められます。
これらを総合的に見極め、自塾に合った代行会社を選ぶことが、SNS集客を成功に導く大きな鍵となります。
7. まとめ
近年、塾の集客においてSNSは欠かせない存在です。
生徒や保護者の多くが日常的にSNSを利用する今、情報を発信することで自然な接点をつくり、信頼関係の構築につなげられます。
SNSは低コストで始められ、継続的な発信によってファンを育て、認知を拡大できる点が大きな魅力です。
一方で、成果を出すためには媒体ごとの特性理解やデザイン・分析などの専門的なノウハウ、そして継続的に発信を続けるリソースが欠かせません。
そのため、専門知識を持つ代行会社の活用も有効です。
「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスでは、SEOの豊富な知見と最新のAI技術を活かし、他社にはない独自の価値を提供しています。ホームページから無料診断にもご応募いただけますので、SNSを単なる宣伝ではなく信頼構築の場として活かすために、ぜひ活用を検討してみてください。