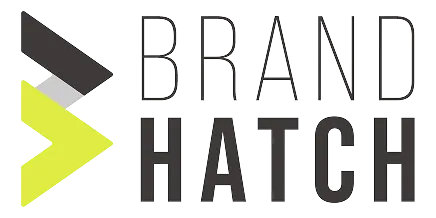SNSは企業にとって強力な情報発信ツールですが、一方で運用には注意点もあります。
公式アカウントの不適切な投稿が、ブランドの信用を失墜させた事例も少なくありません。
炎上をはじめとしたさまざまな注意点やリスクを理解したうえで運用しなければ、逆効果になる可能性もあるのです。
そこで本記事では、企業がSNSを運用する際の注意点や実際の失敗例、対策などを解説します。
SNS運用をこれから始める方や、担当に任命されたばかりの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1. 企業がSNSを運用する際の4つの注意点

企業のSNS運用には、おもに4つの注意点があります。
トラブルを未然に防ぐための基礎知識として、それぞれの注意点をくわしく解説します。
1-1. 炎上のリスク
SNSにおける炎上は、SNS担当者の不用意な投稿やアカウント操作のミスが引き金となり、わずかな時間で広範囲に拡散します。
その結果、企業の信頼やブランドイメージに深刻なダメージを与えることも少なくありません。
特に、差別的・攻撃的な表現や、政治や宗教に関する発言、ジェンダーに対する無配慮な言葉などは、炎上の原因になる可能性が高いでしょう。
また、個人アカウントとの切り替えミスによる「誤爆」も見過ごせない問題です。
SNS担当者のプライベートな内容を、企業の公式アカウントで誤って発信し、取り返しのつかない事態に発展するケースもあります。
NGワードの設定だけでなく、SNS担当者が倫理的な判断力を身につけることや、チェック体制を整えることも重要です。
1-2. セキュリティのリスク
アカウントの乗っ取りや情報の不正利用は、企業の信用を一瞬で損なう深刻なリスクです。
具体的な手口としては、不審なリンクを使ってパスワードを盗み取る「フィッシング詐欺」や、ウイルスを仕込んだファイルで端末を乗っ取る「マルウェア感染」などが挙げられます。
特に、推測されやすいパスワードを使い回している場合は、アカウントへの侵入は容易です。
万が一、アカウントが乗っ取られれば、不正な投稿や詐欺リンクが発信されることで、顧客の信頼を大きく損なう恐れがあります。
1-3. 情報漏洩のリスク
SNSを通じた情報漏洩は、社内の不注意から容易に発生しうるリスクです。
特に、投稿写真に社外秘の資料が映り込んでいたり、顧客・従業員の個人情報が意図せず公開されたりすることもあります。
投稿前に確認していれば防げるものですが、確認不足のまま公開されれば、損害賠償や行政指導といった深刻な事態に発展しかねません。
SNS運用に関わるすべての担当者が、投稿前のチェックの徹底と、機密情報への意識を高く持たなければならないのです。
1-4. 法的なリスク
著作権や肖像権、景品表示法といった法律への理解が不足していると、知らないうちに違法行為を犯すこともあります。
例えば、インターネット上で見つけた画像を許可なく使ったり、動画に市販の音楽を無断で使ったりする行為は、著作権侵害です。
また、人物が写っている写真や動画を投稿する際には、肖像権への配慮も欠かせません。
さらに、2023年に規制が強化されたステルスマーケティング(ステマ)にも注意が必要です。
インフルエンサーなどに依頼した投稿であるにもかかわらず、「広告」「PR」といった表示をせず、あたかも第三者の感想であるかのように見せかけると、景品表示法違反として行政処分の対象となります。
参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(消費者庁)
2. 各SNSで企業が特に注意するべき点

SNSの種類によって、運用時に注意するべき点は異なります。
ここからは、主要な4つのSNSで特に注意するべき点を解説します。
2-1. X(旧Twitter)
X(旧Twitter)では、投稿が意図せず急速に拡散し、炎上に発展するリスクが特に高い点に注意が必要です。
X(旧Twitter)の大きな特徴は、拡散性と即時性です。
問題のある投稿がひとたび出回ると、企業の意図とは無関係に瞬く間に広まり、炎上が制御できなくなる恐れがあります。
特に、担当者による誤爆(アカウント切り替えミス)や不用意な投稿は、ほかのSNSよりも格段に速く拡散され、大きな批判を招きかねません。
また、X(旧Twitter)は全角140文字以内の短文でやり取りされることが多いため、文脈や意図が伝わりづらく、誤解や炎上の火種となりやすいといえるでしょう。
参考:X
2-2. Instagram
Instagramは、画像や動画による視覚的訴求が前提となるSNSのため、素材の選定や管理における注意が特に求められます。
企業アカウントでは、ブランドの世界観を伝えるために高品質なビジュアル表現が重視されますが、一方で「どこから得た素材か」「撮影許可はあるか」といった確認作業は軽視されがちです。
インターネット上の画像や動画を安易に使ったり、イベント写真に第三者が写り込んでいたりする場合、意図せず著作権や肖像権を侵害するおそれがあります。
Instagramではこうしたリスクが発生しやすいため、素材の出所や使用許諾の有無を確認する仕組みづくりが必要です。
参考:Instagram
2-3. TikTok
TikTokの場合、楽曲の使用条件を誤解したまま投稿すると、著作権侵害に発展するリスクがあります。
TikTokは、ショート動画に音楽を組み合わせた投稿が基本であり、企業用アカウントも一般ユーザーと同じ操作感でコンテンツを作れます。
しかし、実際は商用利用が禁止されている楽曲が多く、一般ユーザーが使える流行曲でも、企業が使うと違反になるケースが少なくありません。
そのため、TikTokを企業で活用する際には、プラットフォームの規約やライセンス状況を参照し、素材が使えるものかどうかを確認することが重要です。
参考:TikTok
2-4. LINE
LINEは個別対応が中心のSNSのため、誤配信ややり取りでの誤解がトラブルに発展しやすい特徴があります。
具体的には、次のような問題が発生する可能性があるでしょう。
- 本来一部の顧客にだけ送るべき内容を、全体に一斉配信してしまう
- SNS担当者が感情的に対応してしまい、スクリーンショット付きで外部に晒される
- 絵文字やスタンプなどのカジュアルな表現が誤解を招き、「軽んじられた」と受け取られる
このように、LINE特有の親しみやすさが、企業としての信頼を損なうきっかけになりかねません。
やり取りの一つひとつが公開されうる前提で、誤送信の防止やトーンの管理の徹底が求められます。
参考:LINE
3. 企業のSNSで実際にあった2つのトラブル事例

SNS運用のトラブルはどの企業にとっても他人事ではありません。
ここでは実際に起きた2つの事例を取り上げ、企業が直面した具体的なトラブルとその要因を解説します。
自社に置き換えて考えることで、リスクの本質をより深く理解できるはずです。
3-1. 人気アパレルチェーンの顧客対応における不適切投稿
2024年、とある大手アパレルチェーンの公式Xアカウントが、顧客からの要望に対して「『破れないストッキング』は都市伝説、陰謀論の領域です。作れるんなら作ってます」と投稿し、炎上に発展しました。
ユーモアを交えた表現のようにも思えますが、実際には顧客を小馬鹿にするような口調として受け取られ、「高圧的」「理解がない」といった批判が殺到したのです。
顧客の悩みに共感する姿勢を欠いた対応は、共感を重視するSNS利用者から強い反発を招きました。
企業アカウントにおける言葉遣いとトーンの重要性、そして顧客視点の欠如がブランド価値をいかに損なうかを示す典型例といえるでしょう。
3-2. 大手菓子メーカーのなりすましアカウントによるフィッシング詐欺
とある大手菓子メーカーでは、公式X(旧Twitter)を模倣した巧妙な「なりすましアカウント」が出現し、大規模なフィッシング詐欺が発生しました。
この偽アカウントは、見た目や投稿内容、キャンペーン情報などを精巧にコピーし、ユーザーに対して当選の旨のダイレクトメッセージを送信したそうです。
企業側は事態を受けて、公式サイトや正規アカウントでの注意喚起、SNS運営会社への報告といった緊急対応に追われることとなりました。
対応を誤れば、正規のキャンペーンに対する信頼も揺らぎ、顧客との関係性に大きなダメージを与えかねなかった事例です。
4. 企業がSNSのリスクを防ぐ4つの対策

SNSのリスクには、発生してから対応するのではなく、あらかじめ備えることが大切です。
ここでは、企業が今すぐ実行すべき4つの対策を解説します。
4-1. SNS運用ガイドラインを作る
SNSのリスク対策の土台となるのが、SNS運用ガイドラインの整備です。
SNS運用ガイドラインとは、公式SNS運用に関わるすべての従業員が共通して守るべきルールを明文化したものです。
投稿内容のチェック体制を全社で統一することで、リスクを防ぐ仕組みとして機能します。
また、投稿する時間帯や言葉遣いなどの運用方針全般をまとめておけば、SNS担当者にとっての手引書としても活用できるでしょう。
SNS運用ガイドラインの内容や作り方は次の記事で解説しているため、あわせてご覧ください。
関連記事:【ひな形あり】企業のSNS運用ガイドラインとは?7Stepの作り方も解説
4-2. 担当者任せにしない
SNS投稿は、担当者ひとりの判断で行うべきではありません。
ヒューマンエラーによる炎上や誤爆は、企業アカウントにおけるリスクの最たるもので、複数人による承認フローがその防止策として有効です。
基本となる体制は、担当者が原稿を作成し、上長や別の責任者が内容を確認・承認するダブルチェック方式です。
より厳密な運用が必要な場合には、広報部や法務部によるトリプルチェック体制を採用することで、法的リスクやブランド毀損リスクへの備えを強化できるでしょう。
4-3. アカウントのセキュリティ設定を徹底する
企業のSNS運用では、不正ログインやアカウント乗っ取りによる情報漏洩・詐欺行為を防ぐために、セキュリティ設定の強化も欠かせません。
最も基本的かつ効果的な対策が、二段階認証の設定です。
IDとパスワードに加え、認証コードの入力を必須とすることで、不正アクセスのリスクを大幅に下げられます。
そのほかにも次のような対策が重要です。
- 安易なパスワード(「123456」「誕生日」など)を使用しない
- 大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた強固なパスワードを設定する
- 異なるサービス間でパスワードを使い回さない
アカウント設定やパスワード管理を定期的に見直す習慣を持つことも、不正アクセスの防止につながります。
4-4. SNS担当者へのリテラシー研修を実施する
SNSのリスクを防ぐためには、実践的なリテラシー研修の実施が重要です。
どれだけガイドラインや承認フローを整えても、担当者が正しい知識と判断力を持っていなければ有効に運用することは難しいでしょう。
研修には、次のような観点を含めると効果的です。
- 一度の投稿が企業の信頼に直結するリスクや、投稿の削除が難しい点への理解
- 著作権や肖像権、ステルスマーケティング規制など、SNS特有の法的ルールの把握
- 他社の炎上事例をもとにした「何が問題だったか」を考えるケーススタディ
- 自社ガイドラインの内容を読み合わせ、実際の運用でどう適用するかを確認する時間の確保
判断に迷った際に正しい対応を選べる力を育てることを意識しましょう。
とはいえ、SNSのリスク対策は多岐にわたり、すべてを自社でカバーするのは大きな負担となります。
「運用体制の構築まで手が回らない」という場合は、SNS運用を専門家に任せることもご検討ください。
「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスでは、グループ会社「株式会社ブリジア」がSEO業界で培った分析力と「記事作成No.1」と評されるライティング力で、炎上リスクを抑えつつ共感を呼ぶSNS運用を実現します。
まずは、貴社の課題を分析する無料診断にぜひお申し込みください。
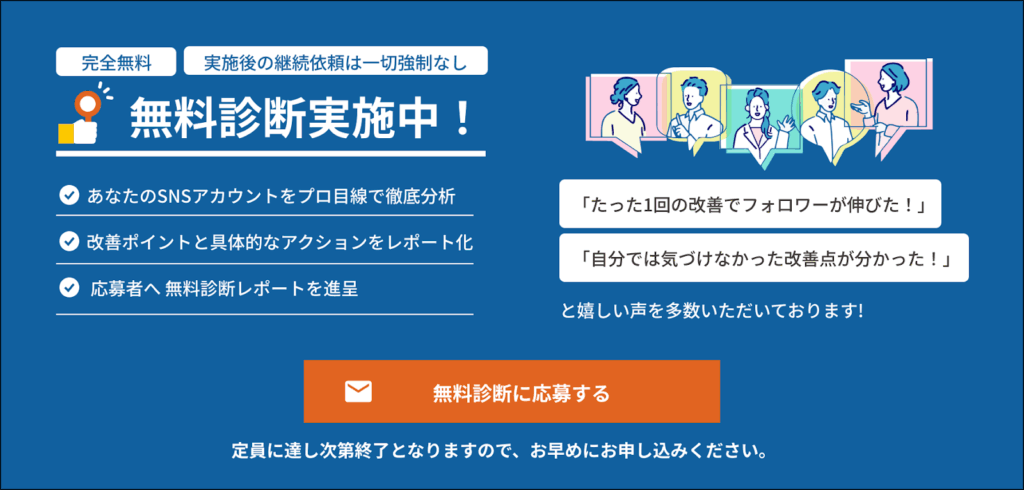
5. 企業のSNSアカウントでトラブル発生!被害をおさえる5Step

どれだけ予防策を講じていても、炎上は予期せぬタイミングで発生する可能性があります。
重要なのは、問題発生後にパニックに陥らず、冷静かつ迅速に組織として対応することです。
ここでは、企業の評判と信頼を守るための5ステップを解説します。
5-1. 【Step1】状況を把握する
トラブル発生時の初動で最も重要なことが、正確な情報を迅速に集めることです。
状況を誤って判断すれば、対応そのものが的外れになり、二次被害を招くおそれがあります。
把握すべきポイントは次の通りです。
- 拡散している媒体(X・Instagramなど)
- 批判の内容と論点(具体的に何が問題視されているのか)
- 拡散の規模と速度(リポスト数、キーワード投稿数などの時系列変化)
判断を誤らないためにも、初動では事実ベースで状況を冷静に見きわめる姿勢が重要です。
5-2. 【Step2】社内に共有する
被害を最小限に食い止めるために、決められた報告ルートに沿って関係部署へ速やかに共有しましょう。
問題を発見した担当者が独断で対応したり、抱え込んだりすることは極めて危険です。
具体的には、次のような報告の流れが望ましいでしょう。
- 第一発見者がスクリーンショットなどで証拠を保存し、上長や広報部に連絡する
- SNS運用ガイドラインなどに沿って、法務・広報・経営層へ情報を共有する
- 継続的な共有のため、チャットツールなどで専用スレッドを立ち上げ、リアルタイムで情報を更新する
特に、漏えいした情報に個人データが含まれる場合、個人情報保護法に基づき、事態を覚知してからおおむね3~5日以内に個人情報保護委員会へ報告する義務が生じる可能性があります。
そのため、速さと正確さを両立させた対応が不可欠です。
5-3. 【Step3】対応方針を決める
情報収集と社内連携が整ったら、次にするべきは対応方針の判断です。
この段階は、企業の信頼回復に直結する極めて重要な局面であり、状況ごとに最適な対応を見極める必要があります。
下記に、代表的なケースと推奨される対応方針をまとめました。
それぞれの状況に応じて、どのような姿勢で対応するべきかを判断する参考にしてください。
| 状況 | 推奨対応 | 注意点 |
| 明確に自社に非がある場合 | 真摯な謝罪・訂正 | 原因説明と再発防止策の提示が必要 |
| 事実無根・少数意見による批判 | 静観または反論 | 感情的反応を避け、冷静に事実を確認して対応 |
| 内容が調査中・判断不能な場合 | ホールディング対応 | 「現在確認中」と発信し、期待値を調整 |
| 個人情報などが含まれる投稿の場合 | 速やかな削除 | 理由と説明を必ず添えて実施 |
特に投稿の削除は、説明もなく行うと隠蔽と捉えられかねないため、慎重さが求められます。
5-4. 【Step4】公式声明を発表する
謝罪や訂正を行う場合は、どの媒体で何を発信するかが信頼回復のポイントになります。
声明は、単なる「申し訳ございません」では不十分です。
具体的には、次のような要素を盛り込んでください。
- 宛先の明示(「お客様各位」「関係者の皆様へ」など)
- 明確な謝罪(誰に対して何を謝罪しているか)
- 経緯説明(事実ベースで、時系列にまとめる)
- 原因分析と責任の所在(組織の問題として説明する)
- 再発防止策(具体的な対応内容を明記する)
- 発表者の責任名義(代表取締役など)
発表は公式Webサイトで行うことが基本ですが、炎上が発生したSNS上でも発信しましょう。
また、画像形式ではなく、テキスト形式での公開が望ましいです。
5-5. 【Step5】モニタリングして再発防止策を実行する
炎上後の対応が一段落した後も、SNS上の反応を継続的にモニタリングすることが重要です。
批判的な投稿が減少しているかどうか、再燃や新たな問題提起が発生していないか、さらには該当投稿のスクリーンショットが他ユーザーによって再共有されていないかなど、状況を追いましょう。
状況によっては、追加の対応や補足説明が必要な場合があるためです。
具体的には、最初の声明では触れていなかった情報が後から判明した場合や、謝罪文が「誠意に欠ける」といった批判を招いた場合などが挙げられます。
また、トラブルを一過性の出来事で終わらせず、組織全体の改善につなげることも大切です。
例えば、SNS運用ガイドラインの見直しや、投稿前の承認フローの強化など、具体的な再発防止策を実行しましょう。
単に火消し対応に終始するのではなく、原因を明確にし、同様のトラブルを繰り返さないための仕組みを作ることが重要です。
6. リスク回避だけで終わらせない!SNS運用を成功させる3つのポイント

企業のSNS運用では炎上させないためのリスク管理が重視されがちですが、それだけでは不十分です。
SNS運用の目的は、ブランドの認知拡大や顧客との関係構築など、企業活動に貢献する成果を生むことにあります。
そこで本章では、トラブルを防ぎつつ成果を最大化するために、意識するべき3つのポイントを解説します。
6-1. SNS運用の目的を明確にする
SNS運用に失敗する原因の一つに、目的が曖昧なまま始めてしまうケースがあります。
目的が明確でなければ、投稿内容に一貫性がなくなり、担当者の判断にも迷いが生じるでしょう。
その結果、ユーザーに価値のない投稿が続いたり、投稿の反応に一喜一憂して軸のない運用に陥ったりするなど、成果につながらない状態が慢性化するおそれがあります。
そのため、SNSを運用する際は、企業として何を達成したいのかという視点を明文化することが欠かせません。
具体的には、次のような目的が挙げられます。
| 目的 | 具体的な狙い |
| ブランド認知度の向上 | 製品・サービスをより多くの人に知ってもらう |
| リード(見込み顧客)の獲得 | SNSからWebサイトや問い合わせへ誘導し、顧客リストを構築 |
| 採用活動の強化 | 社風や職場の魅力を発信し、求職者への訴求力を高める |
| 顧客との関係構築(ファン化) | ユーザーとの対話や共感によって、ブランドへの愛着心を育む |
さらに、上記の目的に連動して「KPI(重要業績評価指標)」を設定することで、運用の成果を客観的に評価可能です。
例えば「認知度向上」が目的なら、投稿がどれだけ表示されたかを示す「インプレッション数」や何人に届いたかを示す「リーチ数」が、「顧客との関係構築」が目的なら「いいね数」や「コメント数」などが該当します。
6-2. 炎上を恐れすぎず、ターゲットに寄り添う
リスク管理を徹底するあまり、「炎上を絶対に避けたい」という心理が強くなりすぎると、SNSの魅力である「共感しやすさ」や「親しみやすさ」を引き出せなくなります。
多くの成功事例に共通するのは、投稿にSNS担当者の個性がにじみ出ていることです。
一方的で形式的な発信ではなく、人が運用していることが伝わる投稿は、ブランドへの好感につながります。
無論、これは好き勝手な発信を許容するということではありません。
公式SNSのトーン&マナーを守りながら、次のような工夫を加えることが重要です。
- 「焼きたてのパン、よい香りです」「今日は撮影日。社内がざわざわしてます」など、日常感のある言葉で距離感を縮める
- ターゲットの関心に合った話題や表現を選ぶ(学生向けなら試験や部活、主婦層なら時短・節約ネタなど)
- ハッシュタグ投稿や口コミによって、ユーザーとの双方向コミュニケーションを強化する
共感や親しみやすさを感じさせる投稿を続けて、ブランドへの信頼や好意を積み重ねましょう。
6-3. 分析と改善を継続する
「投稿して終わり」にしてしまうと、具体的な成果が把握できず、改善につながりません。
継続的に改善するためには、投稿結果を数値で分析し、次の施策に反映させるサイクルが不可欠です。
そのための基本的な考え方が、「PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)」です。
SNS運用においては、次のように活用します。
| ステップ | 内容 | 具体例 |
| Plan(計画) | 運用目的やKPIをもとに、投稿のテーマ・形式・投稿時間などを設定する | 「商品の使用シーンを紹介する投稿を平日朝に行う」など |
| Do(実行) | 仮説に沿って投稿する | 仮説ごとに複数パターンの投稿を作成して実行する |
| Check(評価) | SNSの分析機能やツールで投稿結果を評価する | いいね数・コメント数・保存数・クリック率(CTR)などを比較する |
| Action(改善) | 分析結果をもとに改善点を明確にし、次の投稿設計に活かす | 「実写写真の投稿は保存率が高い」「金曜夜は反応が少ない」などの傾向を把握する |
仮説と検証の繰り返しによって、成果につながる運用体制を着実に築けるでしょう。
7. まとめ
企業のSNS運用には、発信力が大きいからこそ、多くの注意点がともないます。
不適切な投稿や情報管理の不備が、わずかなきっかけで企業の信用を損なう事態につながることも少なくありません。
そのため、安全なSNS運用体制を整えることは、企業にとって重要な経営課題です。
そのうえでSNSをビジネス成果につなげるためには、データに基づく戦略的な運用が不可欠となります。
「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスは、「SEO × 記事作成No.1 × AI活用」を強みとし、企画から戦略的なPDCA運用までを一気通貫でサポートします。
サービス内容や実績をまとめた資料を無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。