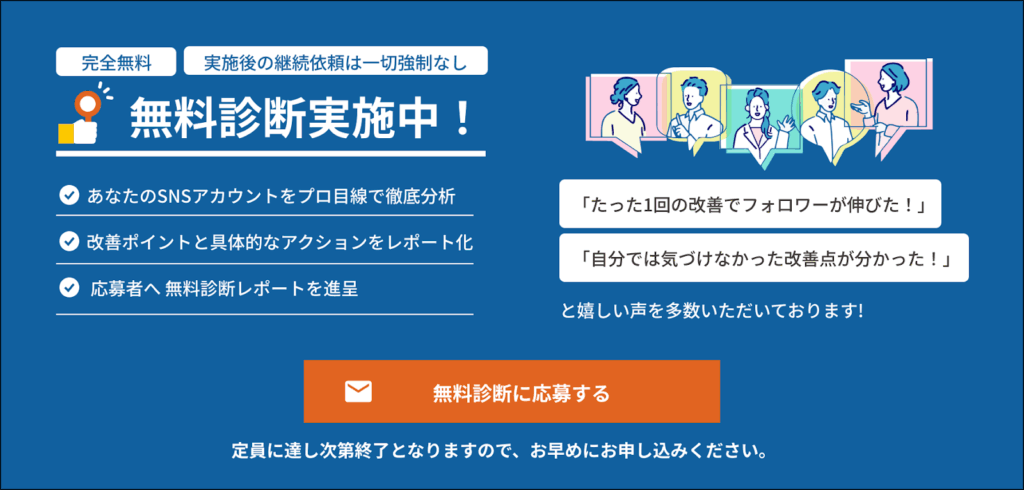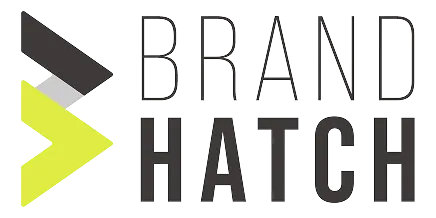「SNSを運用している企業が増えているけど、どのようなメリットがあるの?」
「SNS運用に興味があるけれど、どう始めればよいかわからない」
このような悩みを抱える企業担当者は少なくありません。
SNS運用には認知の拡大・顧客との関係性構築・採用活動への活用など、さまざまなメリットがあります。
しかしその一方で、運用リソースの確保や炎上リスクへの備えなど、適切な知識なしでは、かえって企業の信頼を損なうおそれもあるのです。
本記事では、企業がSNSを運用するメリット・デメリットや、主要SNSの選び方、炎上事例と対策などを解説します。
SNS運用に悩む方や、これから始めようと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
1. 企業のSNS運用とは?SNSマーケティングとなにが違う?

企業のSNS運用とは、情報発信だけでなく、顧客との関係構築を目的とした継続的な取り組みを指します。
本章では、その具体的な役割と、混同されやすいSNSマーケティングとの違いを解説します。
1-1. 企業のSNS運用とは
企業のSNS運用とは、情報を投稿するだけの業務ではありません。
企業の公式アカウントを通じてユーザーと継続的にコミュニケーションを取りながら、信頼や親しみを積み重ねていく活動全体を指します。
SNSは、商品やサービスを一方的に発信する場ではなく、ユーザーとの関係を深める場として活用することが重要です。
そのためには、日々の運用において次のような取り組みが求められます。
- アカウントの管理:プロフィール文やビジュアルの最適化、投稿スケジュールの設計などを行う
- コンテンツの作成・投稿:ユーザーにとって価値のある情報を企画・制作し、定期的に発信する
- コミュニケーション対応:コメントやDMへの返信、UGC(ユーザーの投稿)へのリアクションなど、双方向のやり取りを行う
- 分析・改善:エンゲージメント率やフォロワー数の推移などを分析し、投稿内容や運用方針を見直す
こうした日常的な活動を積み重ねることで、ユーザーから信頼や共感を得られ、ホームページへのアクセスや購買といった行動にもつながりやすくなります。
1-2. SNS運用とSNSマーケティングの違い
SNS運用は「信頼関係の構築」が目的であり、SNSマーケティングは「売上などの成果」を目的とした施策です。
SNS運用では、アカウントの管理や日々の投稿・対話を通じて、既存のフォロワーとのつながりを深めていきます。
信頼や親しみを積み重ねることで、ユーザーが長く関わり続けてくれる環境をつくることが目的です。
一方、SNSマーケティングは、広告配信やインフルエンサーの起用といった、より広範な施策を通じて売上向上を目指します。
SNSを効果的に活用するには、「信頼を築く活動」と「成果をあげる施策」のそれぞれの役割を理解したうえで、両方をバランスよく進めることが大切です。
2. 企業がSNSを運用する5つのメリット

SNS運用にはどのような効果があるのでしょうか。
この章では、企業がSNSを活用することで得られるメリットを解説します。
2-1. 潜在顧客に情報を届けられる
SNSの大きな特徴は、圧倒的な拡散力です。
従来のテレビCMやWeb広告では届きにくかった層にも、SNSなら友人のシェアなどを通じて情報が届く可能性があります。
例えば、X(旧Twitter)のリポスト機能などによって、一つの投稿が瞬く間に多くの人の目に触れることも珍しくありません。
総務省の「令和6年通信利用動向調査」によれば、日本のインターネットユーザーの81.9%が何らかのSNSを日常的に利用しています。
特に10〜40代ではその割合は9割を超えており、SNSで「バズる」ことによる宣伝効果は絶大です。
このように、SNSは自社の存在を知らない潜在顧客へ自然な形でアプローチでき、ブランドの認知を広げるうえで有効なツールなのです。
2-2. 企業のファンを育成できる
SNSには、企業とユーザーの距離を縮め、継続的に関係を深めることで、自社のファンを増やす効果があります。
コメントへの丁寧な返信や、DMへの真摯な対応といった日々のやり取りは、ユーザーに安心感や親しみを与えるでしょう。
また、製品開発の舞台裏や社員の声、現場の日常などを発信することで、企業の考え方や姿勢が伝わり、共感も得やすくなります。
さらに、こうしたファンがよい口コミを発信してくれれば、それが新たなファンの獲得につながる好循環をも生み出すでしょう。
2-3. Webサイトへ集客できる
SNSは、自社サイトやECサイトへの導線としても効果を発揮します。
投稿に商品ページへのリンクを掲載したり、プロフィール欄に公式サイトのURLを記載したりすることで、関心を持ったユーザーをスムーズに誘導できるのです。
さらに、Instagramのショッピング機能など、SNSから商品ページへアクセスできる仕組みも活用できます。
通勤中にスマートフォンで投稿をチェックしたり、休憩時間にタイムラインを眺めたりと、SNSは日常生活に深く根付いています。
投稿がユーザーの目に触れる機会も多いため、大幅なアクセス増加も期待できるでしょう。
2-4. 採用活動につながる
採用活動を強化するうえでも、SNS運用は有効です。
株式会社リソースクリエイションが20代の求職者を対象に実施した調査では、86.1%が「企業のSNSアカウントは必要」と回答し、8割が就職活動中にSNSで企業名を検索した経験があると回答しています。
また、同調査では会社選びで重視する点として最も多かった回答は「働いている人/社風」(87.6%)でした。
これは、会社の日常を伝える内容をSNSに投稿することの重要性を示すデータです。
参考:【573名に調査】転職活動を行う20代の86.1%が企業のSNSアカウントは必要だと回答(PRTIMES)
さらに、SNSで継続的に情報を発信することで、今すぐ転職を考えていない人や、就職活動前の学生といった、将来の応募者層からの関心も高められるでしょう。
2-5. ユーザーのリアルな声を知れる
SNSは、ユーザーのリアルな意見が集まる貴重な情報源でもあります。
口コミやコメント欄に寄せられる感想などから、商品やサービスへの満足度、改善すべき点、新たなニーズなどを読み取れるのです。
こうした声を収集・分析する手法は「ソーシャルリスニング」と呼ばれ、その結果をマーケティングや商品開発に活かす企業もあります。
さらに、寄せられた声をもとに商品を改良し、その内容をSNSで発信すれば、ユーザーに「声が届きやすい企業」と認識してもらえるでしょう。
3. 企業がSNSを運用する2つのデメリット
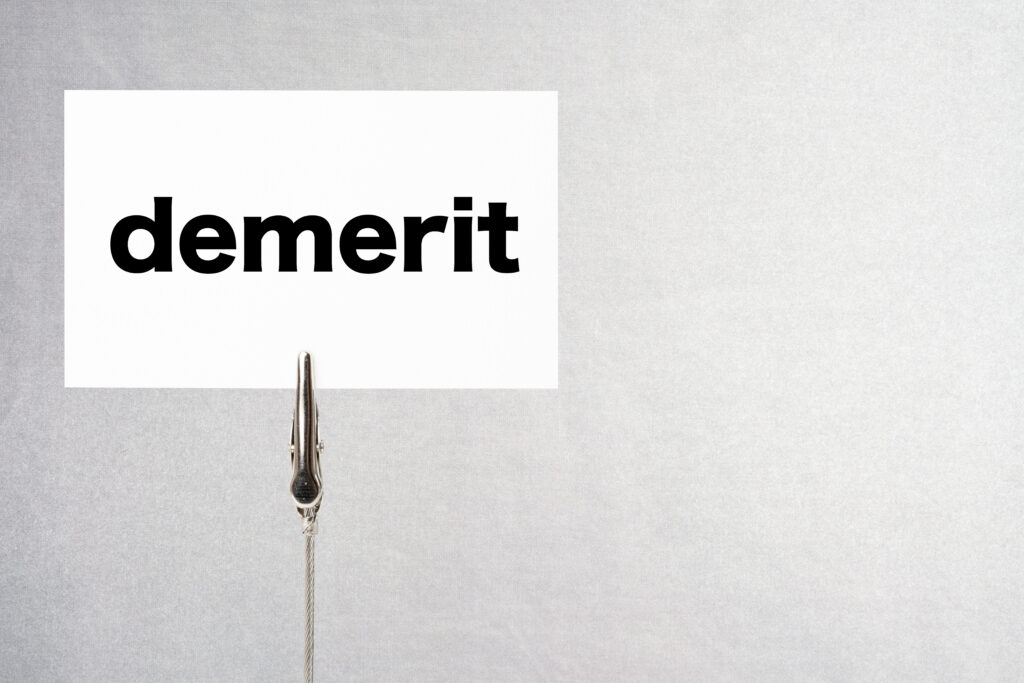
SNS運用には多くのメリットがある一方で、担当者が直面しやすい課題も存在します。
ここでは、特に注意すべき2つのデメリットを解説します。
3-1. すぐには成果が出ない
SNS運用は、短期間で成果が出る施策ではありません。
アカウントを開設してすぐにフォロワーが急増したり、投稿が話題になったりするケースはごく一部で、多くの場合は数ヶ月以上かけて効果が表れます。
その理由のひとつは、SNSはユーザーとの信頼関係を築きながら発信を継続することが前提のメディアだからです。
継続的な発信と丁寧なコミュニケーションを通じて、フォロワーの反応が安定し、企業の認知度も徐々に広がっていきます。
そのため、短期的な成果を求めて途中で運用をやめると、本来積み上げられるはずだったブランド価値や見込み顧客との接点を失うリスクがあります。
SNS運用では、すぐに効果が出なくても焦らず、長期的な視点で取り組む姿勢が欠かせません。
3-2. コンテンツを制作・運用するリソースが必要になる
SNSは始めやすい一方で、継続的な運用には多くの業務がともないます。
コンテンツの企画・制作に加え、投稿スケジュールの管理・コメント対応・データ分析など、日常的な作業はさまざまです。
特に質の高い情報を継続して発信するためには、十分な時間と人手の確保が欠かせません。
投稿が止まったり、ユーザーからのコメントに返信できなかったりすれば、ユーザーとの関係性が薄れ、アカウントへの信頼も低下するでしょう。
また、リソース不足のためにSNS運用を一人の担当者に任せてしまうと、投稿の内容や雰囲気がその人の判断に左右されやすくなり、トーンにばらつきが生じる可能性もあります。
対応漏れや炎上時の混乱など、リスク管理の面でも課題が生じる可能性があるでしょう。
なお、日本企業のSNS運用チームは2〜5名体制が最も多く、全体の約半数を占めるという調査結果もあります。
このことから、最低でも二人以上で対応できる体制が望ましいでしょう。
4. 企業におすすめな6つのSNSの特徴

どのSNSプラットフォームを選ぶべきかで迷う方も多いでしょう。
ここでは、企業が活用するべき6つのSNSの特徴を解説します。
4-1. X(旧Twitter)
▼こんな企業におすすめ
- 旬な情報やキャンペーンを素早く届けたい企業
- ユーザーとの対話を通じて親近感や信頼感につなげたい企業
X(旧Twitter)の特徴は、情報をリアルタイムで発信できるスピード感と、リポスト機能による拡散力の高さです。
イベントやキャンペーンの告知はもちろん、時事ネタやトレンドに合わせた投稿を通じて話題を集めたい場面でも活躍します。
また、企業の担当者がアカウント運用の「中の人」として、少しくだけた語り口で投稿するスタイルは、ユーザーとの距離を縮めやすく、ブランドへの親しみを育てる効果もあります。
ただし、X(旧Twitter)はタイムラインの流れが速いため、投稿が表示される時間も短くなりがちです。
1日複数回の投稿を継続できる体制が求められるでしょう。
参考:X
4-2. Instagram
▼こんな企業におすすめ
- 商品やサービスのデザイン性に自信がある企業
- ブランドの雰囲気や価値観を伝えたい企業
Instagramは、写真や動画などのビジュアルコンテンツを中心に発信するSNSです。
Instagramのユーザーは主に「おしゃれ」「共感できる雰囲気」といった感覚的な魅力を重視して投稿を閲覧するため、見た目の印象が大きく影響します。
そのため、ファッション・コスメ・旅行・グルメなど、視覚的な魅力が購買意欲につながりやすい業種と相性がよいことが特徴です。
またInstagramでは、最大90秒の縦長ショート動画「リール」や、24時間で消える短時間の投稿機能「ストーリーズ」などを活用できます。
これらはタイムライン以外の場所にも表示されやすく、気軽に視聴されやすい形式であるため、より多くのユーザーの目に留まるでしょう。
さまざまな動画で社内の日常や製品の制作過程を発信すれば、企業の雰囲気や価値観が伝わり、フォロワーとの距離を縮められます。
参考:Instagram
4-3. Facebook
▼こんな企業におすすめ
- BtoB商材を扱う企業
- 特定の地域や顧客層に絞って情報を届けたい企業
実名登録が基本のFacebookは、ユーザー情報の信頼性が高い点が特徴です。
また、総務省情報通信政策研究所の「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によれば、ユーザー層は30〜50代のビジネスパーソン世代が中心となっています。
参考:令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(概要)(総務省情報通信政策研究所)
そのため、Facebookは業界向けの情報提供などに活用しやすいSNSといえるでしょう。
さらに、「Facebookグループ」という共通の関心ごとで集まるコミュニティ機能を使えば、特定の業界やエリアに属するユーザーに対して、より深く、継続的にアプローチすることも可能です。
参考:ページ、プロフィール、グループを使用して、Metaのテクノロジーでビジネスを表現する方法(Meta)
「製造業のマーケティング担当者向けグループ」や「○○市の飲食店オーナー向けグループ」などに参加することで、見込み顧客や同業者との接点をつくったり、業界内の情報交換を活性化させたりできます。
参考:Facebook
4-4. TikTok
▼こんな企業におすすめ
- 若年層にアプローチしたい企業
- 動画コンテンツで企業の新たな魅力を伝えたい企業
- 採用広報に力を入れたい企業
TikTokは、エンタメ性の高い短尺動画を中心としたSNSです。
ユーザーの反応がよければ、フォロワー数が少なくてもおすすめ欄に表示される仕組みがあり、動画の質次第で広く拡散される可能性があります。
話題の音楽や映像エフェクトを活用することで、10〜20代のユーザー層に刺さる投稿をつくりやすく、採用活動や企業のイメージアップにも効果的です。
ただし、TikTokはトレンドの移り変わりが早く、視聴者の興味をひくには企画力やユーモア、テンポ感のある表現などが求められます。
参考:TikTok
4-5. YouTube
▼こんな企業におすすめ
- 商品やサービスの魅力を深く伝えたい企業
- 専門知識を発信して業界での信頼性を高めたい企業
YouTubeは、数分〜十数分の動画で詳しい説明ができ、情報をじっくりと伝えられるメディアです。
商品の使い方や活用シーン、専門的なノウハウ、企業の理念や開発ストーリーなどを、映像と音声の両方で丁寧に伝えられます。
動画の内容や構成には一定のクオリティが求められますが、興味関心の高いユーザーに情報をしっかりと届けられるため、購買意欲や企業への信頼を高める効果が期待できるでしょう。
参考:YouTube
4-6. LINE
▼こんな企業におすすめ
- 既存顧客のリピート率を高めたい企業
- クーポンやセール情報で来店を促したい店舗
LINE公式アカウントの最大の強みは、「友だち」登録してくれたユーザーに、メッセージを直接届けられる点です。
ユーザーにはプッシュ通知で情報が届くため、開封率が高い傾向にあります。
この特性から、リピート購入の促進やクーポン配信、予約通知といった、既存顧客との関係を深める施策に最適です。
拡散性はないものの、顧客一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションができるでしょう。
参考:LINE
5. 企業のSNS運用の始め方5Step

SNS運用を成功させるためには、いくつかの段階を踏むことが大切です。
この章では、SNSの運用を始める方法を5ステップで解説します。
5-1. 【Step1】SNS運用の目的を明確にする
SNSを運用する際は、その目的を明確にしましょう。
目的がはっきりしていれば、投稿内容の方針や運用成果の評価方法も判断しやすくなります。
まず、事業全体のゴールに紐づく最終目標として「KGI(重要目標達成指標)」を設定します。
具体的には、「ブランド認知度の向上」や「ECサイトの売上10%アップ」などです。
次に、KGIの達成度を測るための中間指標として「KPI(重要業績評価指標)」を設定します。
「認知拡大」というKGIに対しては、「フォロワー増加数」や「投稿のリーチ数」などがKPIとなります。
重要なのは、フォロワー数など追いやすい数字だけを見るのではなく、その数字が本当にKGIの達成につながるかを考えて指標を選ぶことです。
例えば、「売上アップ」がKGIなのに、「投稿のいいね数」だけを追っても効果の判断にはつながりにくいでしょう。
5-2. 【Step2】ターゲットを設定する
次に、情報を届けたい相手を具体的に設定します。
「30代女性」のような曖昧なものではなく、下記の情報まで細かく設定しましょう。
- 職業
- 居住地
- 抱えている悩みや課題
- 普段の情報収集の方法(検索・SNS・口コミなど)
- ライフスタイルや価値観
これらの項目は、実際の顧客データやアンケート結果など、客観的な情報をベースに作成すると効果的です。
人物像が具体的であるほど、どのような投稿を、どのような言葉で伝えれば響くかが想像しやすくなり、ユーザーからの反応も期待できるでしょう。
5-3. 【Step3】SNSを選ぶ
SNSにはそれぞれ特徴があり、ユーザー層も異なります。
運用目的とターゲットにあわせて、効果が最も見込めるSNSを選びましょう。
例えば、「20代女性向けのファッションブランド」で「認知拡大」を目的とする場合、ターゲットは日頃からInstagramで新商品の投稿をチェックしている可能性が高いでしょう。
このようなケースでは、視覚的な訴求力に優れたInstagramを活用することで、ブランドの世界観を効果的に伝え、興味を引きやすくなります。
特にリソースが限られる場合は、複数のSNSを同時に使うよりも、ひとつのSNSに絞って丁寧に運用した方が、質を保ちやすく成果にもつながりやすいでしょう。
5-4. 【Step4】アカウントのコンセプトを決める
SNSを選んだら、アカウントのコンセプトを決めます。
SNSアカウントは、ユーザーにとって企業との最初の接点になることが多いです。
そのため、プロフィールや投稿の雰囲気から、企業の印象が判断されます。
「信頼できそう」「親しみやすそう」「専門性が高そう」など、ユーザーにどう受け取られたいかを意識してコンセプトを決めましょう。
コンセプトを投稿内容に反映させるためには、言葉づかいやビジュアルのトーンを統一することが重要です。
例えば、専門性や信頼感を重視したい場合は丁寧な言葉づかいと落ち着いたデザインを、親しみやすさを前面に出す場合は絵文字やカジュアルな表現を使うなど、伝え方にも一貫性を持たせましょう。
5-5. 【Step5】データを分析し、運用方法を改善する
SNS運用では、実際の数値をもとに振り返りを行い、投稿内容や運用方法を継続的に改善することが重要です。
成果が出た要因・反応が薄かった要因を分析し、次の施策に活かすことで、アカウントの効果は着実に高まっていきます。
分析の際は、投稿ごとのクリック率やフォロワー数の増減、エンゲージメント率(いいね・コメント・保存など)といった指標を確認しましょう。
また、数値だけではなく、「どのテーマや表現に反応が多かったか」「投稿タイミングは適切だったか」など、ユーザーの行動の背景に目を向けることもポイントです。
こうして得られた気づきをもとに、投稿の切り口・頻度・時間帯・表現方法などを柔軟に見直しながら、運用を調整しましょう。
このPDCA(計画・実行・評価・改善)を回すことで、成果につながりやすくなります。
6. 企業がSNS運用で成果を最大化する3つのコツ

企業がSNSで成果を上げるためには、戦略を立てるだけでなく、どれだけ質の高い活動を継続できるかが重要です。
この章では、SNS運用で成果を最大化するための3つのコツを解説します。
6-1. 社内からネタを発掘する
SNSで発信する情報の中で信頼性がもっとも高く、他社と差別化しやすいのが、実体験や事実に基づく話題です。
例えば、現場の担当者から聞いた話や、商品開発の過程、会社の裏側など、社内でしか知り得ない情報は、ユーザーにとって新鮮で関心を引きやすい話題となります。
具体的には、次のようなネタが有効です。
- 開発者の声: 商品が生まれた背景や、こだわりの技術について語る
- 営業現場の話: お客様との心温まるエピソードや、成功体験を紹介する
- 普段見せない裏側: 工場や制作現場、社内会議の様子などを公開する
- ブランドストーリー: 創業の経緯や理念、ロゴに込めた想いなどを伝える
こうした実際の体験や具体的な場面を伝えることで、「この会社にはどのような人たちが働いているのか」「どのような思いで商品を作っているのか」がわかり、ユーザーの信頼や共感を得られるでしょう。
6-2. 世の中のトレンドや季節ごとのイベントを取り入れる
SNSでは、多くの人が注目している話題や時期に合ったテーマの投稿ほど、ユーザーの目に留まりやすくなります。
そのため、世の中の流行や季節ごとのイベントをうまく活用することは、投稿への反応を高めるうえで効果的です。
例えば、次のような工夫が考えられます。
- X(旧Twitter)のトレンドワードに、自社の商品やサービスを結びつける
- TikTokで人気の音楽や映像効果を使った動画を作る
- バレンタインやクリスマスなどのイベントに合わせて、限定キャンペーンや特別コンテンツを企画する
こうした投稿は、多くのユーザーの関心が集まるタイミングで自社の情報を届けられるため、新たなユーザーとの接点をつくるチャンスになります。
ただし、流行を意識しすぎて本来のブランドの雰囲気とかけ離れた投稿にならないよう注意が必要です。
自社のイメージや伝えたいメッセージに合った形で話題を取り入れましょう。
6-3. ハッシュタグを活用する
投稿をより多くの人に見てもらうためには、ハッシュタグの活用も欠かせません。
ハッシュタグとは、投稿に「#〇〇」の形で付けるキーワードのことで、同じ関心を持つユーザーに投稿を見つけてもらいやすくする役割があります。
効果的に活用するためには、次の点を意識しましょう。
- 投稿内容と関連性の高いキーワードを選ぶ
- 人気ハッシュタグだけでなく、投稿数1万件以下のニッチなものも組み合わせる
- 関連性のあるハッシュタグを3〜10個程度に絞る
このように工夫することで、多くの投稿の中に埋もれにくくなり、関心を持つユーザーに届きやすくなるのです。
7. 企業がSNSで炎上した2つの事例

SNSは強力な拡散力を持つ一方で、使い方を誤れば企業の信用を失うリスクもはらんでいます。
この章では、過去の事例をもとに、どのような投稿が炎上につながるのかを解説します。
7-1. ジェンダーなどに関する配慮を欠いた表現による炎上
社会的な価値観が急速に変化する現代において、ジェンダーなどに対する無自覚な固定観念に基づいた表現が、炎上の引き金になるケースが増えています。
例えば、とある大手家具メーカーが過去に公開したCMで、父と娘がくつろぐ一方、母親だけが奉仕するかのように飲み物を運ぶ描写が「性別による役割の押しつけだ」とSNS上で批判を浴びました。
作り手側に悪意がなくとも、現代の多様な価値観から見て不適切と受け取られる可能性があることを、常に意識する必要があります。
7-2. 不正確な情報発信による炎上
SNSではスピード感が重視されますが、情報の正確性を欠いた発信は、企業の信頼を根底から揺るがします。
例えば、2017年にとあるスポーツ用品メーカーが、ボストンマラソンの完走者に向けてメールを送信しました。
その件名が「おめでとう。ボストンマラソンを生き延びた!」という内容だったため、2013年に同大会で発生した爆破テロ事件を想起させ、世界的な批判を招いたのです。
言葉の意図だけでなく、その言葉が社会的な文脈の中でどう受け取られるか、想像力を働かせることが不可欠です。
8. 企業がSNS運用で炎上を防ぐ3つの対策

SNS運用にリスクは付き物ですが、事前の備えがあれば多くの炎上は未然に防げます。
この章では、日常的なリスク管理と緊急時の対応策を解説します。
8-1. SNS運用のガイドラインを策定する
まず取り組むべきは、社内で共通のルールを定めるSNS運用ガイドラインの策定です。
ガイドラインがあれば、投稿内容やコメント対応の基準が明確になり、担当者が変わっても対応のばらつきが少なくなります。
その結果、担当者の経験や感覚だけに依存した運用にならず、トラブルのリスクも軽減できるのです。
ガイドラインには、主に次の項目を盛り込みましょう。
- 基本方針:SNSの運用目的・守るべき姿勢(誠実さ・法令遵守など)・責任の所在など
- 禁止事項:差別的表現・誹謗中傷・機密情報の漏洩など
- 投稿基準:言葉遣いのトーン・発信する情報の信頼性チェックの方法など
- コメント対応方針:返信する基準・クレーム発生時の報告ルートなど
- 緊急時の対応:炎上発生時の社内連携・報告の手順など
作成したガイドラインは作りっぱなしにせず、運用メンバー全員で定期的に確認し、最新の状況に合わせて更新することが欠かせません。
8-2. 著作権と肖像権の基本を理解する
SNSでは画像や音楽などを気軽に利用できますが、それらには必ず権利が存在します。
他人の著作物や肖像を無断で使うと、法的なトラブルに発展するおそれがあるのです。
著作権については、インターネット上の画像や文章を勝手に転載することは原則禁止であり、他人の投稿を使う際は必ず本人の許可を得なければなりません。
参考:ネット上の著作権トラブル 正しい知識で回避しよう(政府広報オンライン)
また肖像権については、写真や動画に人物が映っている場合、社員や顧客を含め本人の同意なく公開できず、事前に許可を得ることが基本です。
参考:肖像権ガイドライン~自主的な公開判断の指針~(デジタルアーカイブ学会)
こうした知識は担当者だけでなく、運用に関わる全員が理解しておく必要があります。
8-3. ソーシャルリスニングで自社の評判を監視する
炎上の兆候を早期に察知するためには、日々のモニタリングが欠かせません。
その方法のひとつがソーシャルリスニングで、SNS上で自社やブランドに関する投稿を継続的に収集・分析する取り組みを指します。
主な目的は次の3つです。
- 自社名やブランド名に関するネガティブな投稿を早期に発見する
- ユーザーの不満やクレームの兆候をいち早く把握する
- 炎上リスクの火種を見つけ、迅速に初期対応につなげる
専用ツールを導入しなくても、Xの検索機能などを使って自社名を定期的に検索するだけで、最低限の監視は可能です。
こうした取り組みを継続することで、問題が大きくなる前に気づけ、対応に移りやすくなります。
9. 企業がSNS運用で成功した3つの事例

ここでは、SNS運用で成果を上げている企業の事例をご紹介します。
各社の戦略や工夫から、自社の運用に応用できるヒントを見つけましょう。
9-1. シャープ株式会社

参照:シャープ株式会社
「シャープ株式会社」の公式Xアカウントは、企業のSNS運用成功例として有名です。
最大の特徴は、「中の人」と呼ばれる運用担当者のユーモラスで人間味あふれる発信スタイルにあります。
製品の宣伝にとどまらず、時事ネタや日常の話題も交えながらフォロワーとの自然な対話を継続しています。
他社アカウントとの軽妙なやりとりは度々話題となり、企業の好感度を飛躍的に高めました。
参考:@SHARP_JP(X)
9-2. 北欧、暮らしの道具店

参照:北欧、暮らしの道具店
ECサイト「北欧、暮らしの道具店」は、Instagramを活用したブランディングの成功事例です。
商品を直接的に売り込むのではなく、「その商品がある心地よい暮らし」や「豊かな時間」といった世界観を伝えています。
参考:「北欧、暮らしの道具店」が生まれるまで。世界観の作り方、SNS運用の秘訣(SELECK)
このように、ユーザーに「こんな暮らしをしてみたい」と思わせる表現方法は、ビジュアルを重視するInstagram運用の参考例となるでしょう。
9-3. 株式会社三和交通

参照:株式会社三和交通
タクシー会社である「株式会社三和交通」は、TikTokへのユニークな動画投稿によって、企業イメージの刷新と採用活動の活性化に成功しました。
役職者を含む社員たちが、ダンスに全力で挑戦するコミカルな動画が話題を呼びました。
「真面目そうな会社がここまでやるのか」というよい意味でのギャップと、社員が本気で楽しんでいる人間味がユーザーの心を掴んだのです。
この取り組みの結果、企業の認知度が向上しただけでなく、若年層からの応募が急増し、新卒採用の応募数が例年の約2倍になりました。
常識にとらわれない柔軟な発想が、SNSで成功するポイントとなることを示す好例です。
10. 企業がSNS運用に行き詰まったら?2つの対策

SNS運用を続けるうちに、壁にぶつかることもあります。
ここでは、成果が伸び悩んだときの2つの選択肢を解説します。
10-1. セミナーや書籍でスキルアップする
企業がSNS運用に行き詰まったとき、まず取り組むべきは学び直しとスキルアップです。
SNSの世界は変化が速いため、SNS運用に携わる人には常に最新の情報を吸収し、自分の知識を更新することが求められます。
具体的には、オンラインセミナーやスクールで体系的に学ぶ方法があります。
近年では「BUZZ SCHOOL」や「Withマーケ」といった、SNS運用やSNSマーケティングに特化した学習サービスが登場しており、基礎から応用まで段階的に学べる点が魅力です。
また、書籍から実践的なノウハウを得る方法もあります。
具体的には、次のような書籍を読むとよいでしょう。
- 「僕らはSNSでモノを買う」(飯高悠太 著)
- 「PDCAを回して結果を出す!Instagram集客・運用マニュアル」(田中紗代 著)
- 「世界一やさしい Twitter集客・運用の教科書 1年生」(岳野めぐみ 著)
成果が出ないときは、学び直しを通じて運用の方向性や改善点を見つけることが大切です。
10-2. SNS運用代行やコンサル会社に依頼する
社内の人手が足りない場合や、専門的なノウハウが不足している場合は、SNS運用を専門とする外部企業への委託も有効です。
戦略設計から日々の投稿、分析まで、自社の課題に合わせて支援を依頼できます。
外部パートナーを選ぶ際は、次の点を比較しましょう。
- 実績と得意分(自社と同業種での成功事例があるか、依頼したいSNSに強みを持っているかなど)
- 提供サービスの範囲(戦略設計・投稿代行・コメント対応・レポート作成など、どこまで任せられるか)
- 料金体系(月額固定型・成果報酬型など、自社の予算や目標に合ったプランを選べるか)
- 担当者との連携体制(コミュニケーションのしやすさや報告の頻度など)
外部の知見を取り入れることで、社内の担当者はコンテンツ企画や方針の見直しなど、より重要な業務に集中できます。
もしSNS運用を外部に委託する際は、「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスをぜひご検討ください。
SNS・MEO・記事制作を連携させる独自の戦略を駆使し、中小企業や宿泊ビジネスを中心に、数多くの企業のリード獲得や予約増加を実現してきました。
サービスの詳細をまとめた資料も無料でダウンロードいただけますので、ご確認ください。

11. 企業のSNS運用に関するよくある質問

最後に、SNS運用を始めたばかりの担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
日々の運用や方針を検討する際の参考にしてください。
11-1. Q. 担当者は何人くらい必要ですか?
A. 最低でも2名体制での運用をおすすめします。
1名体制では、担当者の不在時に運用が止まってしまったり、投稿内容のチェックが甘くなったりするリスクがあります。
副担当がいることで、人的なミスを防ぎ、安定した運用を継続しやすくなるでしょう。
11-2. Q. BtoB企業でもSNSは効果がありますか?
A. はい、有効です。
株式会社ワンズマインドが実施した「BtoB企業のSNS活用実態アンケート」によると、BtoB企業の93.4%がSNS活用を「必要」だと考えており、実際に活用している企業の53.8%が「効果を得られた」と回答しています。
参考:BtoB企業の93.4%が企業のSNS活用を「必要だと思う」と回答、活用ツールは1位がXで2位YouTube、3位Instagram(PRTIMES)
例えば、導入事例の紹介や業界に特化したノウハウを発信すれば、「この企業は信頼できる」と感じてもらうきっかけになるでしょう。
BtoB企業のSNS運用の詳細は、次の記事で解説しています。
関連記事:中小BtoB企業にSNS活用は必要?成功のヒントが得られる事例も解説
11-3. Q. アカウントが伸び悩んだらどうすればよい?
A. アカウントが伸び悩んだら、SNS運用の目的とターゲットを見直しましょう。
各SNSの分析機能を使い反応のよい投稿の傾向を把握し、投稿内容がターゲットの関心とズレていないかを精査します。
また、競合の成功しているアカウントを観察し、自社に足りない要素を探ることも有効です。
11-4. Q. SNS運用にAIは活用できますか?
A. はい、AIはさまざまな場面で強力な支援ツールになります。
投稿文のアイデア出し、画像・動画の作成、データ分析の自動化など、多岐にわたる業務で活用可能です。
ChatGPTのような生成AIを使えば投稿案を瞬時に作成できますし、コメント分析やDMへの対応の効率化にも活用できます。
AIを上手に活用できれば、担当者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
11-5. Q. 企業アカウントのDMはどう対応すべき?
A. DMには、基本的に迅速かつ丁寧に返信し、対応できない内容は適切な窓口へ案内しましょう。
ユーザーからの問い合わせや要望に早めに返答することで、信頼感を高められます。
一方、リソース不足などで対応できない場合は「DMには返信していません」などとプロフィールに明記するなど、方針をあらかじめ示すことが重要です。
12. まとめ
企業のSNS運用は、単なる情報発信ツールではなく、顧客との関係を築き、ブランドを育て、事業の成長を支えるうえで重要です。
SNS運用を成功させるには、目的とターゲットの明確化から分析・改善までの流れを、着実に進めることが欠かせません。
SNS運用は短期的に結果が出る施策ではありませんが、ユーザーに価値ある情報を継続して発信することで、商品の購入やサービス利用などにつながります。
しかし、いざ自社の状況に置き換えて戦略を立てるとなると、どこから手をつければよいか迷うこともあるでしょう。
そのような場合は、一度専門家に自社の現状を分析してもらうことも有効です。
「Brand Hatch株式会社」では、事業の課題を明確にする「無料診断」も受け付けております。
ぜひご活用ください。