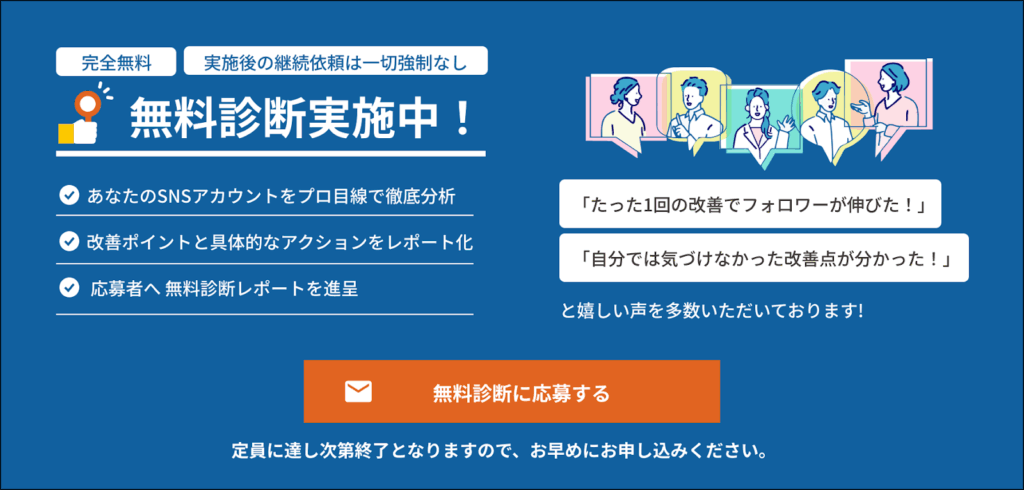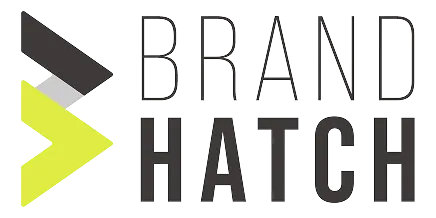「企業のSNS運用ルールは何から手をつければよいのだろう?」
「炎上は防ぎたいけれど、厳しすぎるルールでがんじがらめにはしたくない」
このような悩みを抱える、企業のSNS運用担当者や管理職の方も多いのではないでしょうか。
安全かつ効果的なSNS運用を実現するためには、明確なSNS運用ルールの整備が不可欠です。
ルールが曖昧なままでは、たった一つの投稿が炎上を招き、企業全体の信頼失墜につながることもあります。
そこで本記事では、SNS運用ルールが必要な理由や盛り込むべき重要項目、具体的な作り方、成功事例などを解説します。
何から手をつければよいかわからないと悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
1. 企業にSNS運用ルールが必要な3つの理由
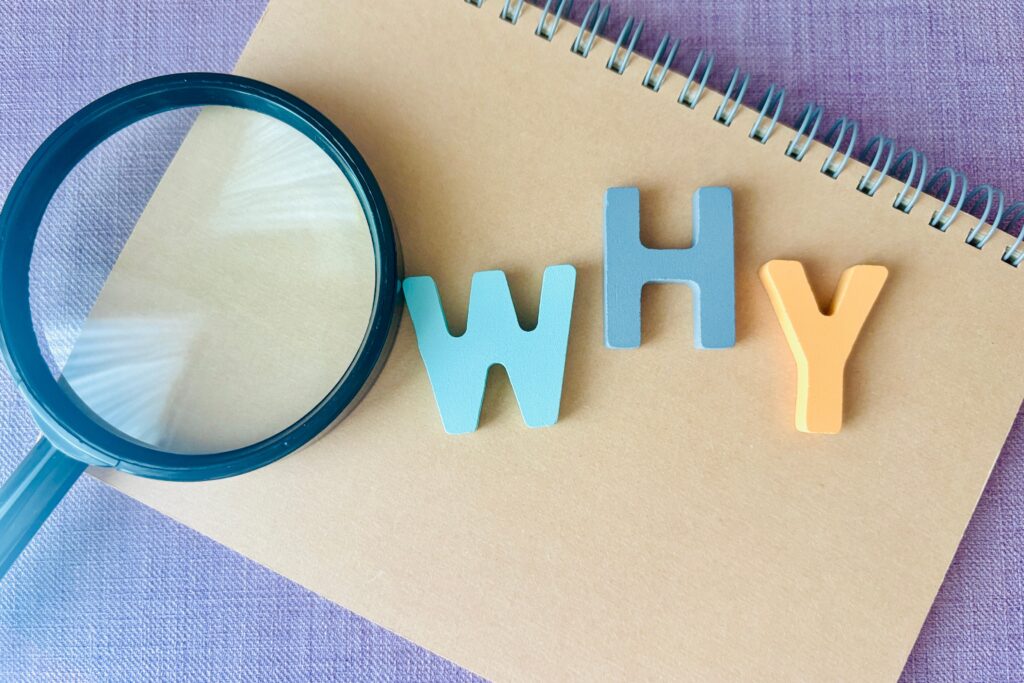
企業がSNSを運用するうえで、明確なルールを設けることは重要です。
ここでは、SNS運用にルールがなぜ必要なのか、その理由を3つの視点から解説します。
1-1. 炎上リスクから会社の評判や価値を守るため
企業にSNS運用ルールが必要な最大の理由は、炎上による信頼の損失や業務への支障を防ぐためです。
株式会社エフェクチュアルの調査によれば、約20%の企業がSNSを起因とする炎上を経験しており 、その結果として「売上の減少(40%)」や「ブランド毀損(36.7%)」といった影響が出ています。
参考:【調査レポート】5社に1社が“炎上”を経験。企業はSNS・口コミ・検索結果の影響にどう備えるべきか?(SORILa)
このようにSNSでの炎上は、一度起これば企業のイメージを損ね、顧客離れや取引停止など、事業に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
たった一つの投稿が、クレーム対応や謝罪対応に追われる事態を引き起こすことも珍しくありません。
だからこそ、禁止事項の明記だけでなく、トラブル発生時の対応フローや連絡体制まで整備することが、企業活動の安定を守るうえで不可欠です。
1-2. 投稿の質を一定に保ち、担当者任せにしないため
SNS運用ルールを設けることで、投稿の内容や品質が担当者によって変わる事態を防げます。
SNS運用を特定の担当者のスキルや感覚に委ねると、担当者が交代するたびに投稿のトーンや内容がぶれ、ブランドイメージも揺らいでしまいます。
SNS運用ルールを定めておけば、「どのような内容を、どのような表現で投稿するか」といった判断を、誰が担当しても一定の基準で行えるでしょう。
また、新しく担当になった人が業務を早く覚えるためのマニュアルとしても役立ちます。
結果として、SNS担当者の負担を減らしながら、企業として安定した発信を継続できる仕組みが整うのです。
1-3. SNSを使う目的をはっきりさせるため
SNS運用のルール作りは、SNS活用の目的を明確にし、事業戦略と連携させるためにも不可欠です。
目的があいまいなままでは、投稿内容に統一感がなく、期待する効果も得られません。
SNS運用ルールの作成は、SNS運用で達成したい目的を整理するよい機会になります。
例えば、「採用活動を強化するために社内の雰囲気を伝える」「商品理解を深めてもらうために使い方を紹介する」といった目的が明文化されていれば、投稿内容の方向性がぶれにくくなり、成果の測定指標も明確になるでしょう。
2. 企業のSNS運用ルールの種類

SNS運用ルールは、対象者や目的によっていくつかの種類に分けられます。
これらの違いを正しく理解することが、実効性のあるSNS運用ルール作りの第一歩です。
2-1. 【担当者向け】SNS運用ガイドライン
SNS運用ガイドラインは、アカウントを運用する担当者向けに、より具体的な業務手順を定めたものです。
実務マニュアルとしての性格が強く、日々の投稿作成から緊急時の対応まで、担当者が迷わずに行動できる基準を示すことを目的とします。
複数人で運用する際の連携もスムーズになり、品質を一定に保つほか、新任担当者の教育資料としても活用できるでしょう。
SNS運用ガイドラインについては次の記事で詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
関連記事:【ひな形あり】企業のSNS運用ガイドラインとは?7Stepの作り方も解説
2-2. 【従業員向け】ソーシャルメディアガイドライン
ソーシャルメディアガイドラインは、全従業員が個人としてSNSを利用する際に守るべき行動指針を定めた、社内向けのルールです。
従業員一人ひとりが企業の一員であるという自覚を持ち、会社の信頼を損なう行動をしないように促すことを目的としています。
私的な発信が原因で起こるトラブルから、従業員自身と会社の両方を守るための重要なルールです。
2-3. 【社外向け】ソーシャルメディアポリシー
ソーシャルメディアポリシーは、企業がSNSをどのような方針で運用しているかを対外的に示す文書です。
SNSを通じた情報発信に対する企業の姿勢を明確にすることで、顧客や取引先からの信頼を得ることを目的としています。
また、万が一炎上などのトラブルが発生した場合にも、企業としてどのような考え方で対応するのかを説明するための基準として機能します。
ソーシャルメディアポリシーをあらかじめ公開することで、誤解や混乱を最小限に抑えられ、担当者も冷静に対応しやすくなるのです。
3. 企業のSNS運用ルールに盛り込むべき要素

3つのSNS運用ルールに盛り込むべき要素はそれぞれ異なります。
この章では、各SNS運用ルールに記載すべき要素を解説します。
3-1. SNS運用ガイドラインの場合
SNS運用ガイドラインは、運用担当者が業務に迷わず取り組めるようにすることが大切です。
具体的には、次の内容を盛り込みましょう。
| 項目 | 盛り込むべき内容のポイント |
| 基本方針とアカウント管理体制 | ・SNSを活用する目的や基本方針 ・運用責任者、承認フロー、パスワード管理方法といった具体的な管理体制 |
| 投稿の品質担保と承認プロセス | ・ブランドイメージに合ったトーン&マナーの定義 ・禁止事項の具体例 ・投稿前の承認手順やチェック体制の明文化 |
| ユーザーとのコミュニケーション方針 | ・コメントやDMへの対応範囲や対応時間帯のルール化 ・好意的、否定的なコメント双方への具体的な返信例 |
| 緊急時・トラブル発生時の対応フロー | ・緊急時の報告ルートと初動対応責任者の明確化 ・社外への情報発信の判断基準や連携方法の定義 |
上記の要素が具体的に定まっていれば、担当者が日々の業務において安心して判断・行動できる環境が整います。
3-2. ソーシャルメディアガイドラインの場合
ソーシャルメディアガイドラインは、全従業員が個人としてSNSを利用する際に守るべき行動基準です。
従業員一人ひとりが会社の信頼を損なう行為を未然に防ぐため、次の要素を盛り込みます。
| 項目 | 盛り込むべき内容のポイント |
| 基本姿勢 | ・SNSでの発言に対する自覚と責任の促進 ・「匿名でも責任が伴う」といった意識付け |
| 機密情報・個人情報の保護 | ・業務上知り得た機密情報や個人情報の投稿禁止 |
| 禁止事項 | ・誹謗中傷、差別的発言などの禁止行為の具体的なリスト化 ・会社や取引先の信用を損なう行動の禁止 |
| 著作権などの尊重 | ・著作権や肖像権を侵害しないための引用ルールの明記 |
| 問題発生時の報告義務 | ・問題発生時の具体的な報告ルートの明示 |
上記の要素をガイドラインとして明文化することで、「何をしてはいけないか」「困ったときは誰に相談すればよいか」などが明確になり、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
3-3. ソーシャルメディアポリシーの場合
ソーシャルメディアポリシーを整備する際は、企業のスタンスや利用範囲を明示する、具体的な要素を盛り込むことが重要です。
企業の透明性と信頼性を高めるために、次の要素を含めましょう。
| 項目 | 盛り込むべき内容のポイント |
| SNS運用の目的 | ・SNS運用の目的の簡潔な説明 |
| 運用方針 | ・誠実な対話や正確な情報提供といった運用方針の明記 |
| 公式アカウント一覧 | ・なりすまし防止のための公式アカウント一覧の掲載 |
| 免責事項 | ・従業員の個人的な発信が公式見解ではない旨の注意書き ・投稿の削除基準など、リスクを限定するための免責事項 |
特に「誰が公式か」「どこまでが企業の責任か」を明確にすることは、SNS時代に不可欠なリスク管理策のひとつです。
4. 企業のSNS運用ルールの作り方4Step

効果的なSNS運用ルールは、担当者一人の判断で作るものではありません。
社内の関係者と協力し、意見を反映させながら、次にご紹介する4つのステップを踏んで構築することが重要です。
4-1. 【Step1】SNSの運用目的を整理する
SNS運用ルールを作る最初のステップは、「なぜこのルールが必要なのか」という目的を明確にすることです。
例えば、「炎上リスクを低減したい」「投稿の品質を安定させたい」「採用活動を強化したい」といった具体的な目的を定めることで、ルールの方向性が定まります。
同時に、ルールの適用範囲を明確にすることも重要です。
例えば、アカウントの運用者のみに適用される「SNS運用ガイドライン」なのか、それとも全従業員の私的利用まで含む「ソーシャルメディアガイドライン」なのか、対象者をはっきりと線引きしましょう。
目的と範囲を最初に整理することで、その後の設計がスムーズに進み、関係者間の認識のズレも防ぎやすくなります。
4-2. 【Step2】SNS運用ルールのたたき台を作る
目的と方針が固まったら、次にルールのたたき台を作ります。
この段階で完成形を目指す必要はなく、社内での議論や見直しの土台となる最初の案を準備することが目的です。
専門用語を避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉で記述しましょう。
また、実際の業務を想定した具体的な例を盛り込むことで、現場の担当者がルールを自分ごととして捉えやすくなります。
例えば、「投稿してはいけない内容の具体例」や「推奨される言葉遣いの例」などを加えると、抽象的なルールが実践的な指針として機能するでしょう。
このたたき台は、次のステップで関係部署の意見を反映させていく際の基礎となるため、実用性を意識して作ることが大切です。
4-3. 【Step3】関係部署の意見を聞く
たたき台をもとに、関係部署との調整を行います。
SNS運用は、法務・人事・広報・IT部門など、さまざまな部署と連携して進めるからです。
例えば、法務部からは著作権や景品表示法に関する指摘が、人事部からは従業員の私的利用に関する配慮が、広報部からはブランドイメージとの整合性に関する意見が出る可能性があります。
また、IT部門はセキュリティやパスワード管理の観点から重要な視点を提供してくれるかもしれません。
このように部署ごとの専門的な観点を取り入れることで、法的な抜け漏れや運用上のリスクを防ぎ、現実的かつ説得力のあるSNS運用ルールに仕上げられます。
このプロセスを丁寧に行うことが、全社的な協力体制を築き、SNS運用ルールのスムーズな導入につながるのです。
4-4. 【Step4】最終調整をして、承認をもらう
各部署との調整が終わったら、集まった意見を反映してSNS運用ルールを最終版に仕上げます。
最終調整の段階では、細かい表現だけでなく、「責任者は誰か」「いつから適用するのか」といった実務的な要素も明確に定めましょう。
また、SNS運用ルールを正式なものとするためには、経営層の承認を得るプロセスが不可欠です。
社長や役員といった経営陣に内容を説明し、「このルールは会社としての公式な方針である」という承認を得ましょう。
経営層の承認があることで、従業員も「自分たちが従うべきルールである」と認識しやすくなり、実効性のあるルールとして運用しやすくなります。
ここまでにご紹介した4つの手順を踏めば、実効性のあるSNS運用ルールを構築可能です。
しかし、日々の業務と並行して、たたき台の作成から関係部署との調整までを担うことは、担当者に大きな負担となる場合も少なくありません。
「Brand Hatch株式会社」のSNS運用代行サービスでは、こうしたルール策定のプロセスから日々の運用代行まで、戦略に基づいた施策をまとめてお任せいただけます。
リソース不足や進め方にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

5. SNS運用ルールを根付かせる3つのポイント

SNS運用ルールは、作成しただけでは意味がありません。
現場に根付かせるためには、これからご紹介する3つのポイントをおさえることが不可欠です。
5-1. 全従業員に周知する
SNS運用ルールが完成したら、社内ポータルへの掲載や全社向けの説明会などを通じて、その存在を全従業員に周知しましょう。
その際には、「なぜこのルールが必要なのか」「どのようなリスクを防ぐためのものか」といった背景を丁寧に説明することで、従業員一人ひとりの理解を得やすくなります。
また、内容を理解したことの確認として誓約書への署名を求めることも、ルールを「自分ごと」として意識させるうえで効果的です。
伝え方を工夫することで、全社でリスクに立ち向かうための協力体制を築くきっかけにもなります。
5-2. 定期的に研修を行う
SNS運用ルールは、一度伝えただけでは定着しません。
従業員が継続的に意識できるよう、研修や情報共有の場を定期的に設けましょう。
例えば、新入社員研修の必須項目にSNSルールの説明を組み込んだり、社内報で定期的に注意喚起を行ったりするなど、継続的な情報共有が効果的です。
また、他社で実際に起きた炎上事例などを題材に勉強会を開くことも、従業員のリスク意識を高めるうえで有効です。
こうした働きかけは、ルールの定着を促すだけでなく、組織全体のSNSリテラシー向上にも直結します。
ルールのこと「存在は知っているが見たことはない」という状態にならないよう、適切なタイミングで繰り返し周知することが不可欠です。
5-3. SNS運用ルールを定期的に見直す
SNS運用ルールは、定期的に内容を見直し、状況に応じて更新することが重要です。
SNSを取り巻く環境や社会の価値観は、日々変化しています。
そのため、SNS運用ルールは一度作って終わりではなく、常に最新の状態にアップデートすることが不可欠です。
例えば、年に1〜2回、定期的にルールを見直す機会を設け、実際の運用で生じた課題や、変更が必要な項目を洗い出します。
そのうえで、「新しいSNSの動向に対応できているか」「最近の炎上事例を踏まえた内容になっているか」「現在の運用体制に合っているか」といった視点でチェックするとよいでしょう。
こうした見直しを定期的に行うことで、現場の状況や実務に即した状態を保ち続けられ、トラブルを予防しやすくなります。
6. まとめ
SNS運用ルールは、単なる炎上防止策ではありません。
企業のブランド価値を守り、従業員の行動を支え、ひいては会社全体の成長に貢献するための仕組みです。
ただし、ルールは作って終わりではなく、全社への周知・定期的な研修・継続的な見直しが欠かせません。
これらの取り組みを自社だけで推進するには、多くの時間と専門的なノウハウも求められます。
「Brand Hatch株式会社」では、中小企業や地域密着型ビジネスに特化し、戦略立案からコンテンツ制作、日々の運用までを一気通貫で支援しています。
どこから手をつけるべきか、何が課題か分からないという方は、ホームページの無料診断やLINE相談をぜひご活用ください。